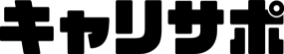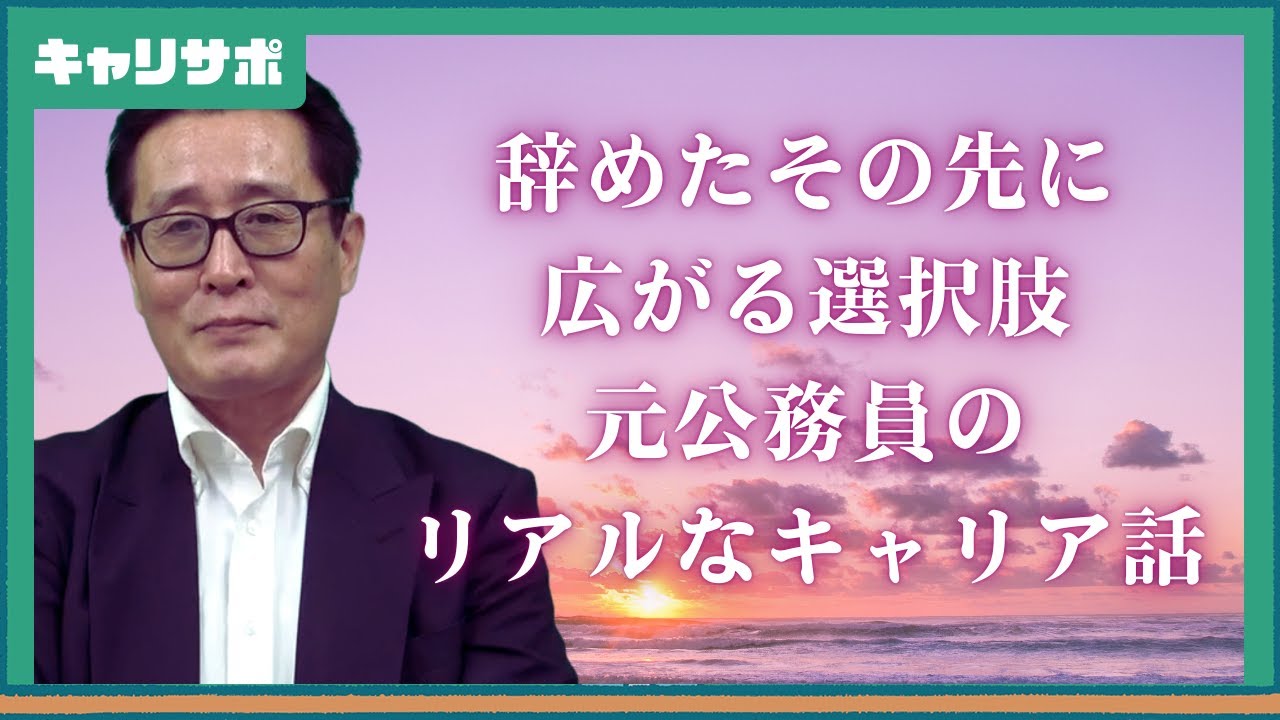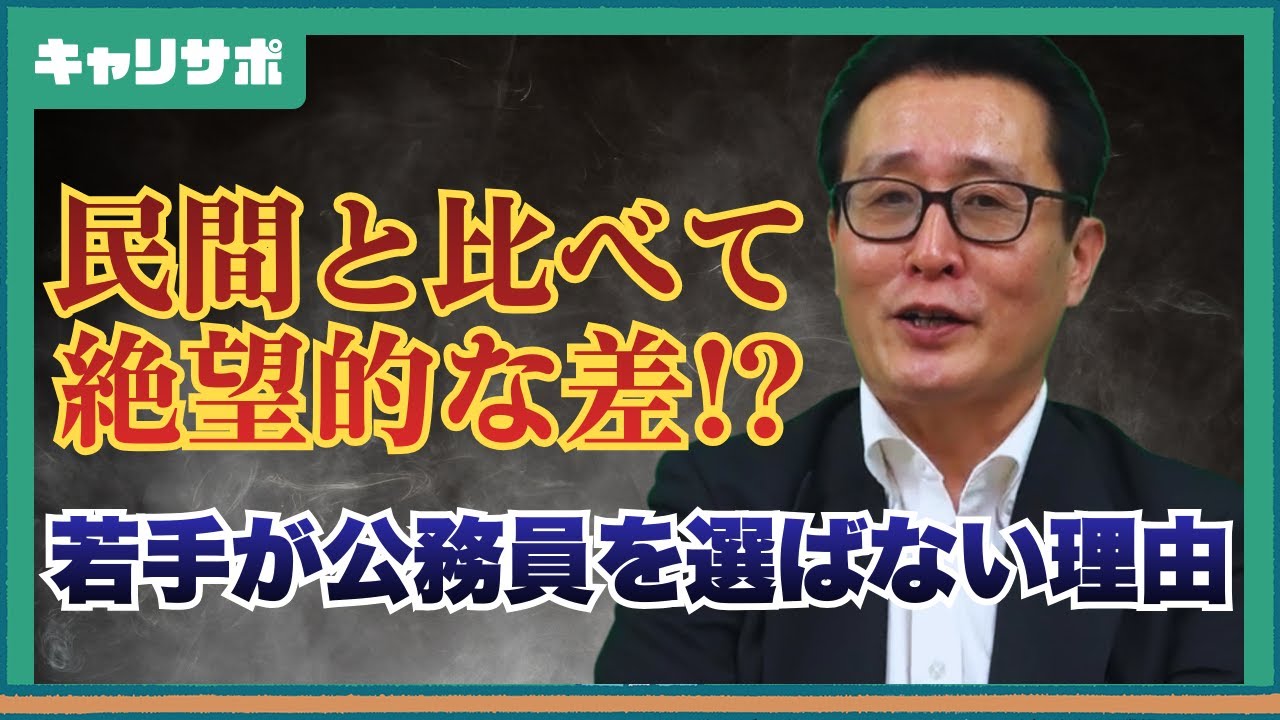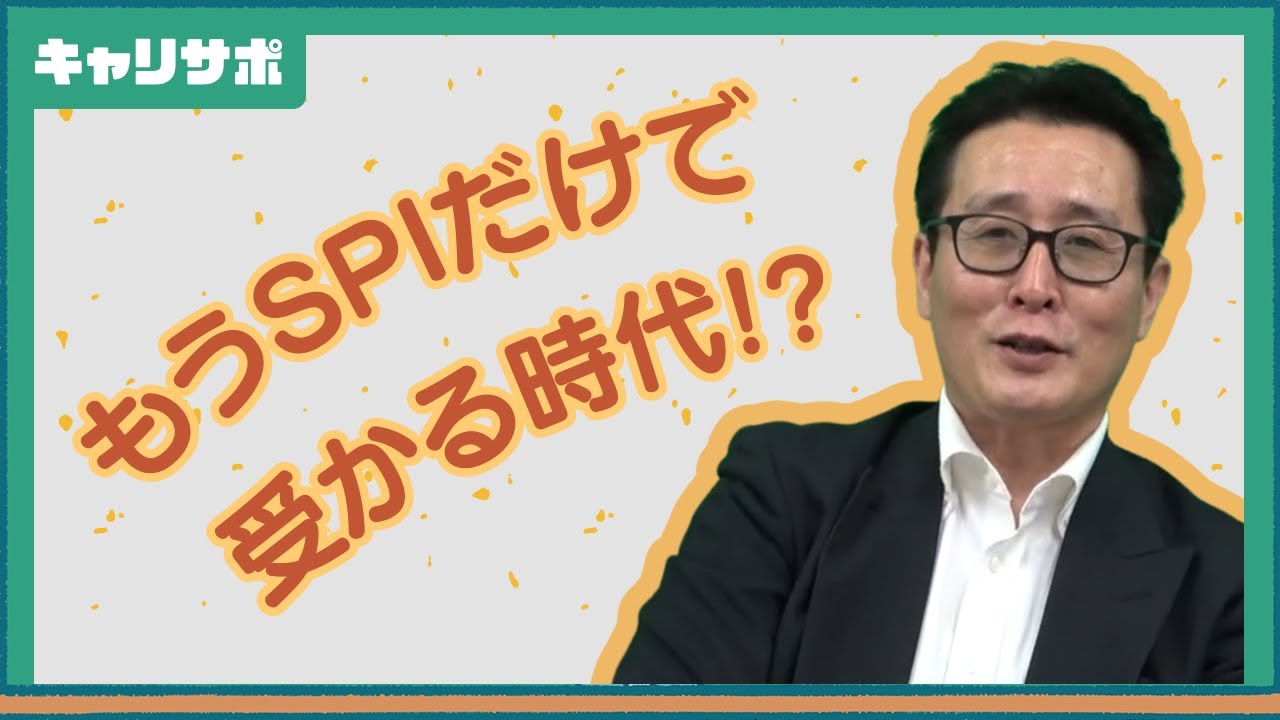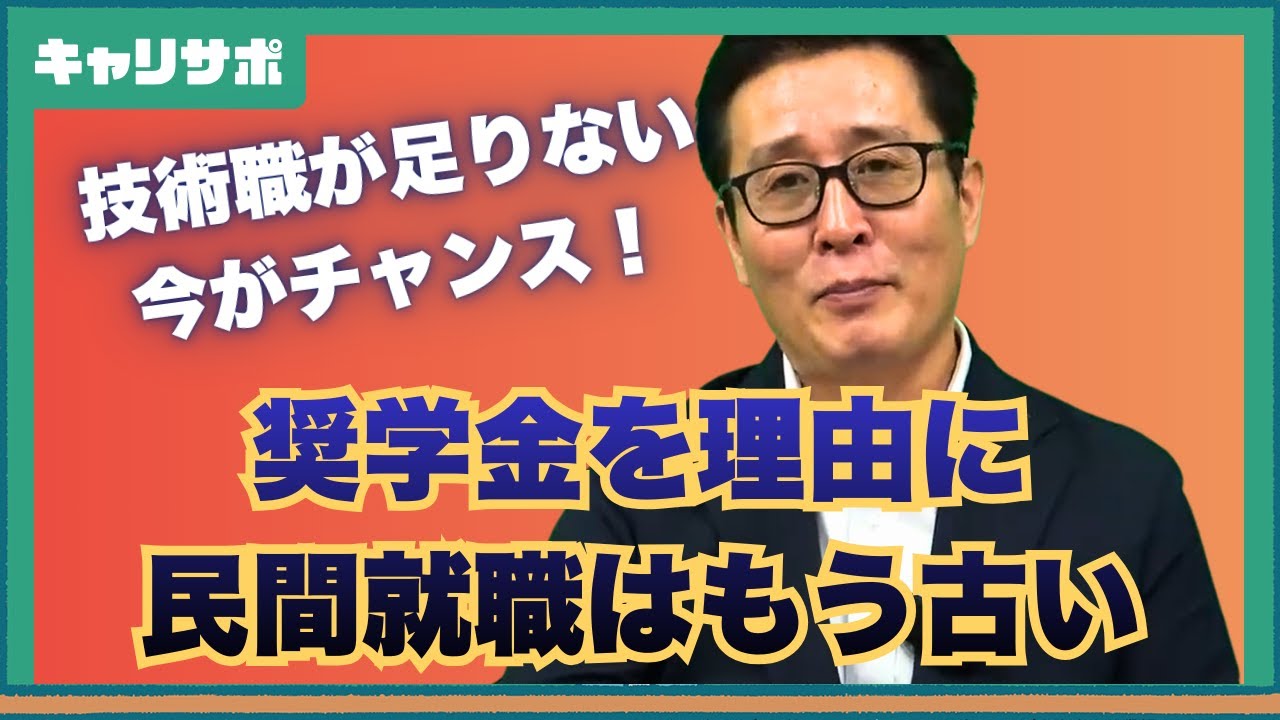【公務員試験】数的処理で事故らないための直前対策&戦略解説
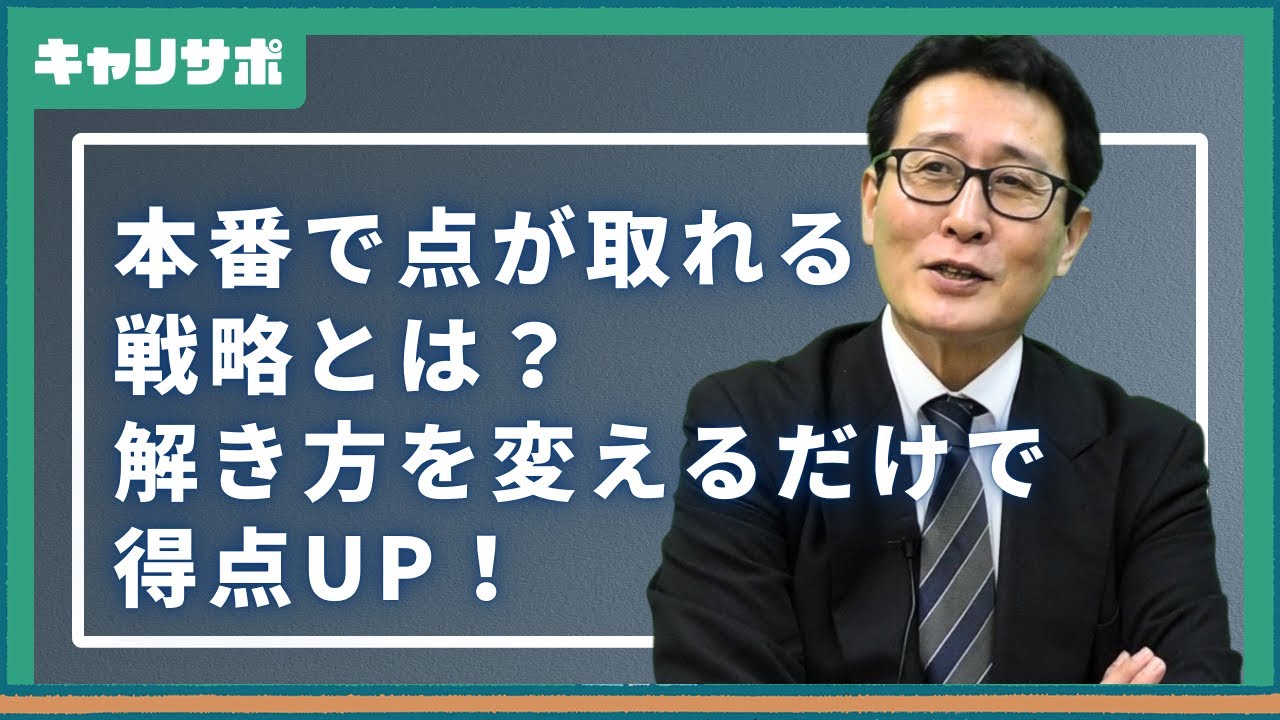
今回は「直前期に数的処理の点数を上げる方法」についてお話ししたいと思います。
キャリサポではこれを「実戦トレーニング」と呼んでいます。簡単に言えば、公務員試験の大きな特徴の一つである「数的処理」という科目に、しっかり対応していこうという話です。
目次
数的処理は事故が起こりやすい!
数的処理が原因で、思わぬ失敗をする受験生が実は少なくありません。
では具体的にどんな事故が起こるのかをご紹介します。
1ミスからパニックに…
例えば、以前にもお話ししたことがありますが、理系の受験生で、都庁の数的処理(全16問)で普段は12〜13点を安定して取っていた子が、本番ではなんと3点しか取れなかったということがありました。
原因は、第一志望の都庁で緊張していたことや、「絶対に数的で点を取らないといけない」というプレッシャーから、最初の1問目・2問目(都庁では集合や対応関係などボリュームのある問題が出ることが多い)でつまずいて、そこからパニックになってしまったということでした。
このことからも、「第一志望の試験を初戦にしない方が良い」「場慣れのためにも前哨戦を受けた方がいい」と私は繰り返し伝えています。
油断からのケアレスミス…
また別の例として、国家総合職に合格し、中央省庁に内定をもらった実力十分の子が、都庁を受けた際に足切りされてしまいました。原因はケアレスミスでした。問題が簡単すぎたため油断し、「この教室で一番早く解き終わって退出しよう」という目標を立ててしまったそうです。その油断が命取りになり、結果は足切りでした。
本番で手が動かなくなってしまう…
他にも、本番で手が動かなくなってしまったという受験生もいました。当時私はブログを運営していたのですが、その子から「午後の試験は受けずに帰ります」との投稿があり、偶然そのタイミングで私がそれを見て、「とにかく最後まで受けてこい」と返信しました。その子は受験を続け、結果的にギリギリで合格しました。
このように、本番では何が起きるかわかりません。だからこそ、数的の対策は万全に行う必要があります。
数的処理の対策
では、具体的にどう対策すべきかご紹介していきます。
①実際に受験する試験の過去問を、時間を測って解く
数的処理については、ただ問題集を解いていても、本番では思うように点数が取れないことがあります。しかし、公務員試験には傾向があるため、過去問の内容は毎年似ていることが多いです。
つまり、「本番に近い形で過去問を解く」ことで実践力をつけていく。これは例えるなら、ゴルフでコースに出るようなものです。「実力で勝負する方法」と「コース(試験傾向)を徹底的に研究して勝つ方法」がありますが、理想はその両方を兼ね備えることです。
②30秒ルール
30秒考えても手が止まったら、その問題はいったん飛ばして次に進みましょう。また、解答が出ても選択肢に該当しない場合も、すぐに次へ。数的処理は、1問にこだわってしまうと、他の2〜3問を解く時間がなくなってしまいます。
③取れそうな問題だけ確実に取る
他にも、こんな戦略もあります。今、教養試験のボーダー点が下がってきているため、「半分作戦」として、取れそうな問題だけを確実に取るという方法です。全部解こうとして焦るより、最初から「半分取ればいい」と割り切って臨むのも一つの手です。
④資料解釈に時間をかける方法
どうしても数的が苦手という人は、「資料解釈(4問)」にしっかり時間をかけて確実に点を取りましょう。これは数的というより、計算問題に近いので、丁寧に解けば点が取れます。
加えて、毎年必ず1〜2問は、勉強していなくても感覚で解けるラッキー問題もあります。そういった問題を逃さずに拾っていけば、十分に合格点に届きます。
実際に、資料解釈で4点取り、感覚的に2〜3点取り、さらに1問ラッキーで正解し、合計16点中10点を超えたという例もあります。逆に、真面目に全問解こうとした子が7〜8点しか取れなかったということもあります。
このように、「最初から全問解く」というスタイルだけでなく、自分の実力やメンタル状況に応じた戦い方を工夫していくことが重要です。
過去問研究が超大事!
そのためにも、受験する試験で数的処理が何問、資料解釈が何問といった出題傾向を、事前に過去問からしっかり研究しておくことが欠かせません。何も知らずに本番に臨むのは、あまりに無謀です。
まとめ
いかがでしたか?
お話したように数的処理は本番で大きな事故が起きやすいです。
本番では何が起こるか分からないので、数的処理の対策はしっかりやっておく必要があります。
そこで今回ご紹介した数的処理の戦略・勉強法を活用してぜひ本番に備えておいてくださいね。
今回のブログの内容の動画はこちら↓