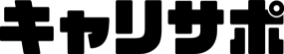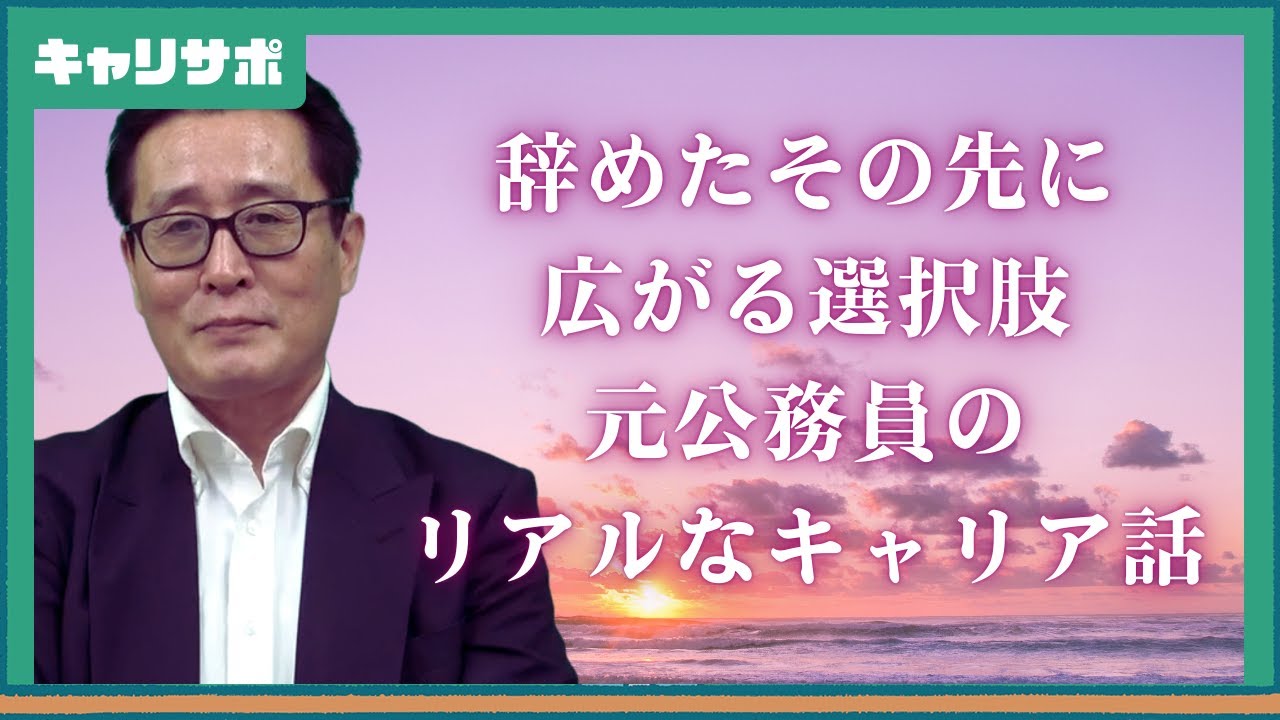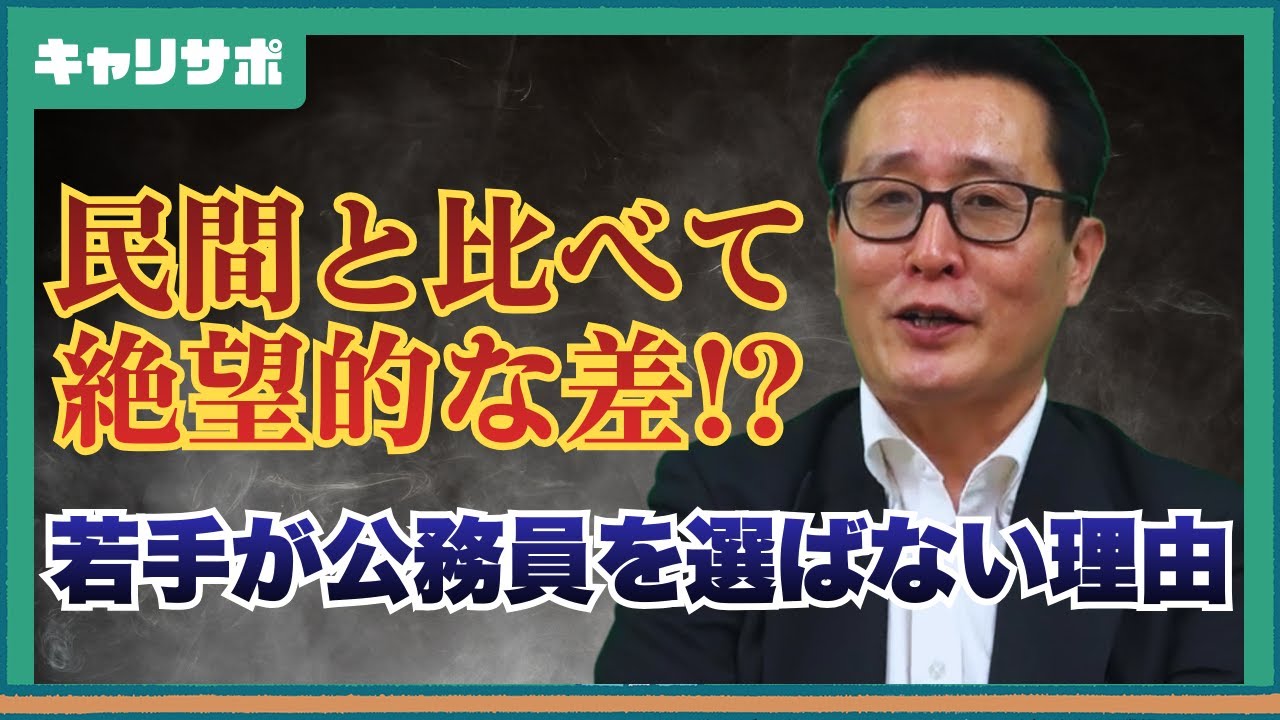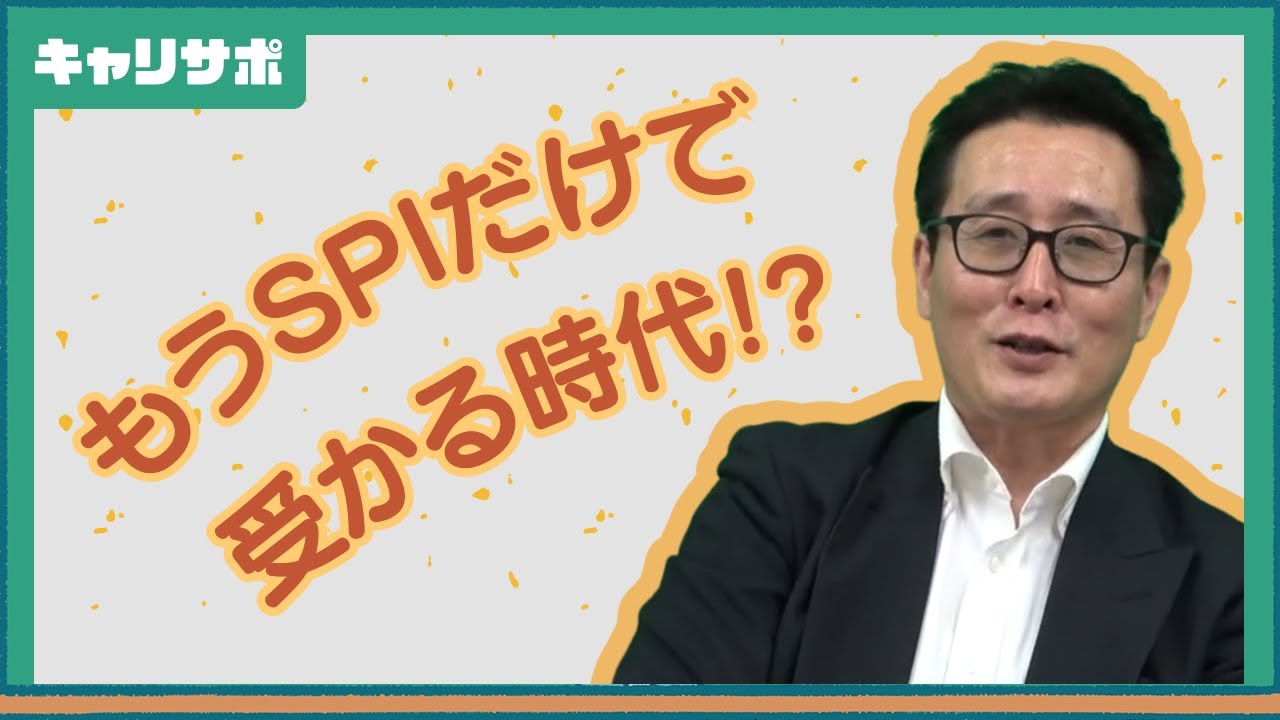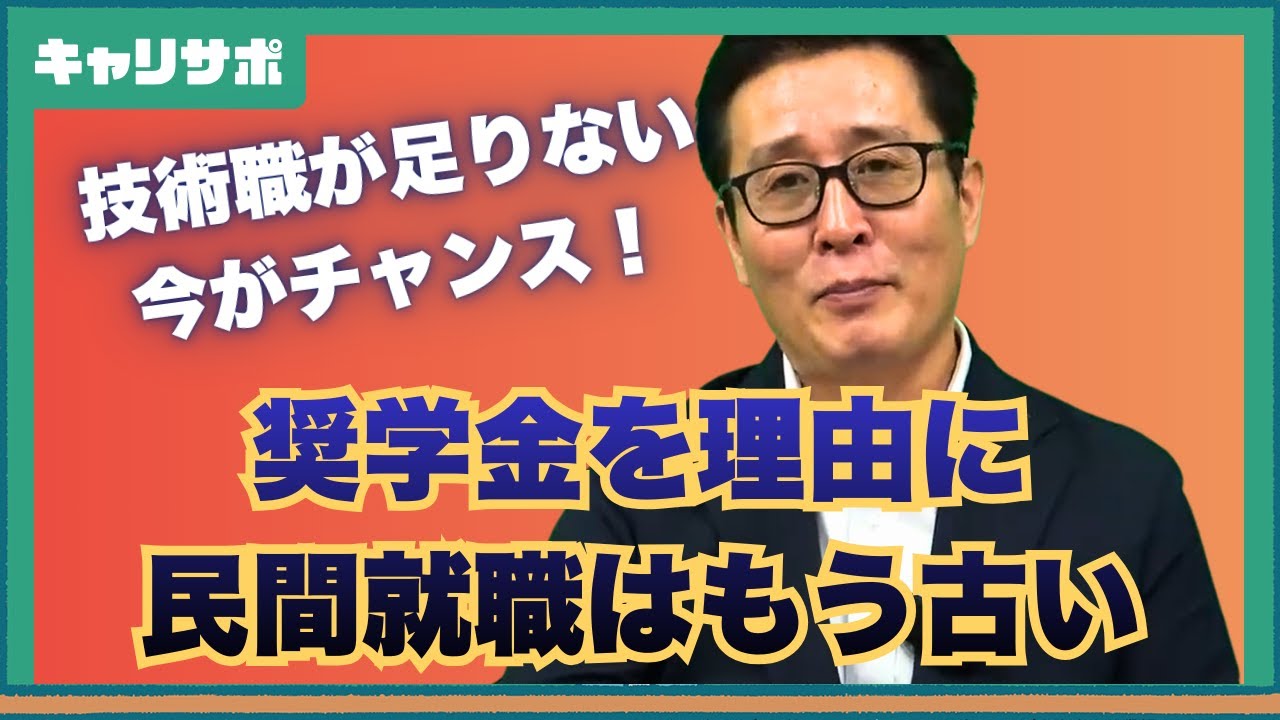【公務員】公務員の兼業ルールとは?今後の働き方が変わる!
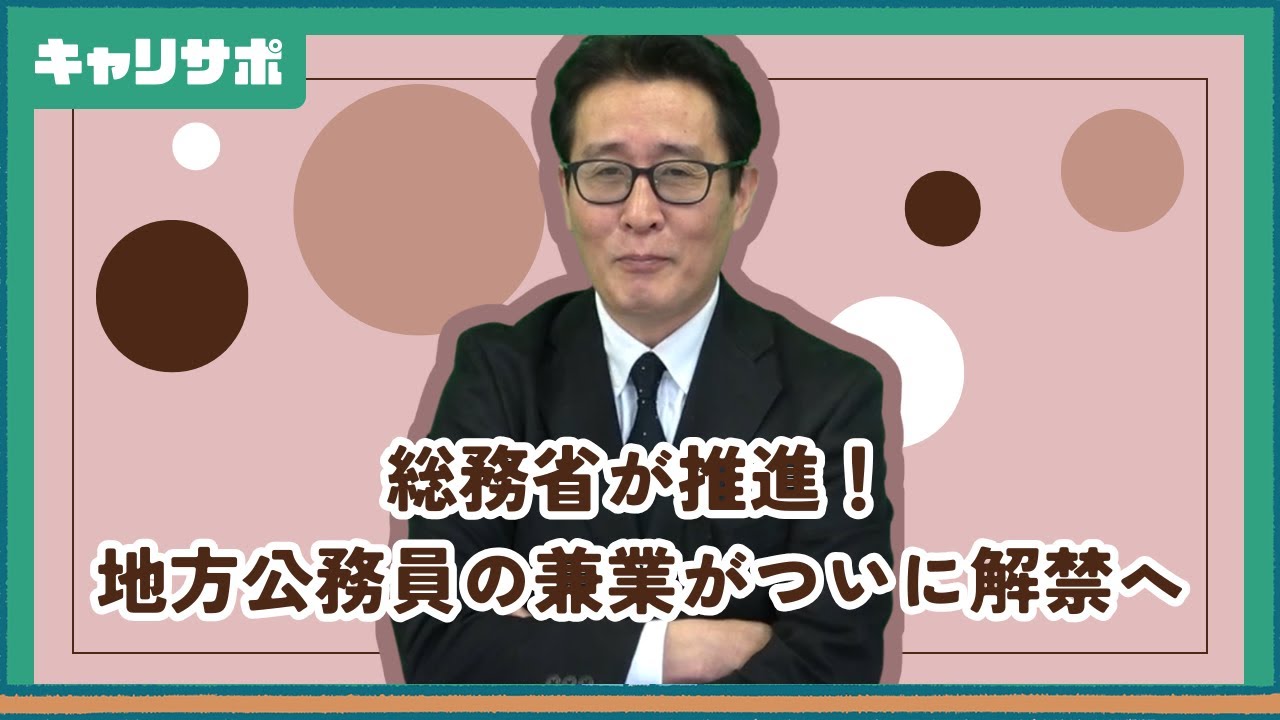
今日は、「総務省が地方公務員の兼業を推奨し始めた」という話題についてお話しします。
目次
現状 公務員の兼業は禁止されている
まず、国家公務員では国家公務員法第104条において、「他の事業または事務への関与」が制限されており、兼業が禁止されています。地方公務員についても、地方公務員法第38条により、「営利企業等への従事制限」があり、同じように兼業が禁止されています。
国家公務員法第104条で「他の事業または事務への関与の制限」とされており、第103条では「私企業からの隔離」などが定められています。このように、公務員の兼業は禁止されているのが現状です。
総務省の公表
今年に入って、総務省が「地方公務員の社会貢献活動に関する兼業」について公表しました。過去にもあった許可制度により、条件を満たせば兼業OKとなるかもしれません。
地方公務員については、
・「公務の能率の促進」
・「職務の公正の確保」
・「職員の品位保持」等
これらのために、許可制が採用されているとされています。
ただし、条件としては
・「営利団体の役員等を兼ねること」
・「自ら営利企業を営むこと」
・「交渉を伴う事業または事務に従事すること」
などが制限されています。
なぜ兼業が推奨されるのか
シンプルに言えば、おそらく兼業が認められないところも人手不足のネックになっているということもあり、総務省がそれを推奨する流れになっているのではないかと思われます。
今年の2月に行われた、国家公務員に対する兼業に関する職員アンケートでは「今後兼業を行いたい」とする回答が32.9%ありました。
これだけ希望者が多ければ、公務員の兼業が認められるようになっていくのではないかと思います。
特に、国家総合職や経験者採用の若手層では、兼業希望の割合が高くなっています。理由としては、
・「自分の趣味・特技等を生かしたい」
・「本業では得られない新しい知見やスキル、人脈を得たい」
などの声が挙がっています。
どんな兼業が可能なのか
たとえば、地方での新聞配達や、過疎地域でのコンビニ店員など、従来は認められなかったような仕事も可能になっていくかもしれません。
また、不動産投資についても、一定の制限のもとであれば認められています。
株式投資については特に制限はなく、自宅の農業や小規模な家業の手伝いなども、問題ありません。
まとめ
総務省が兼業を推進し始めた今、皆さんも将来的にはチャレンジしてみると良いのではないでしょうか。
このブログの内容の動画はこちら↓