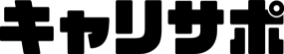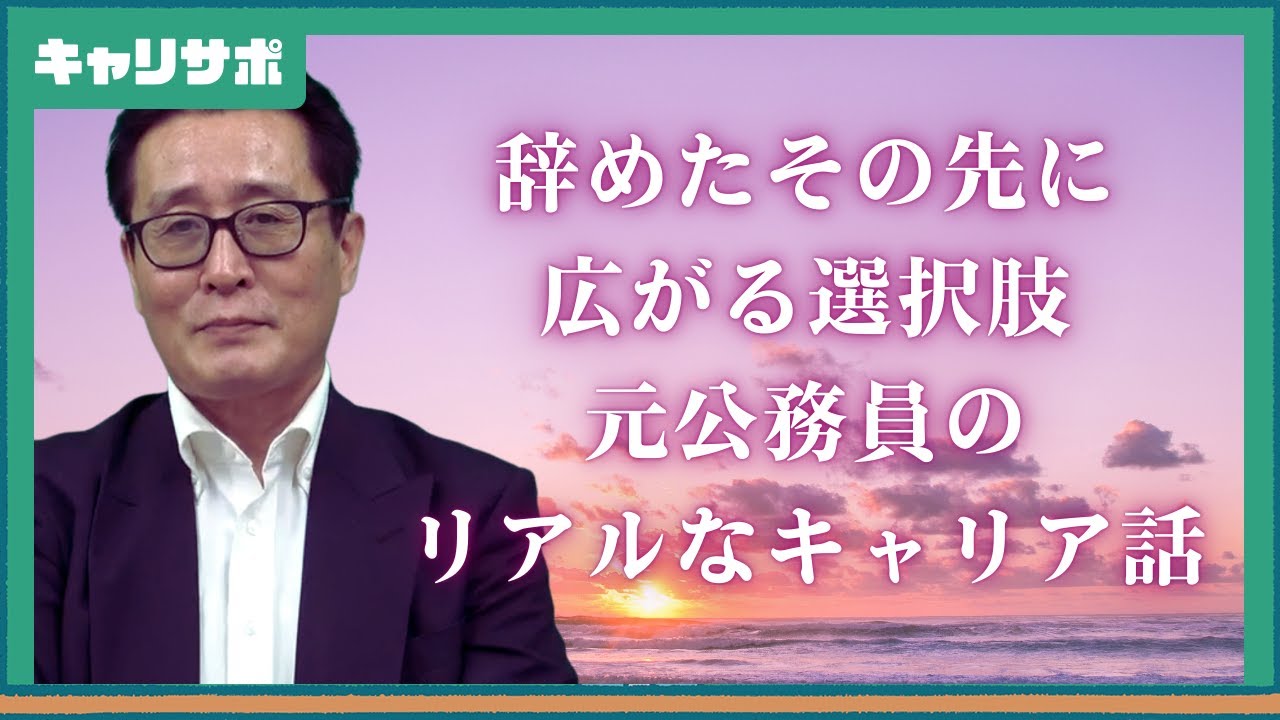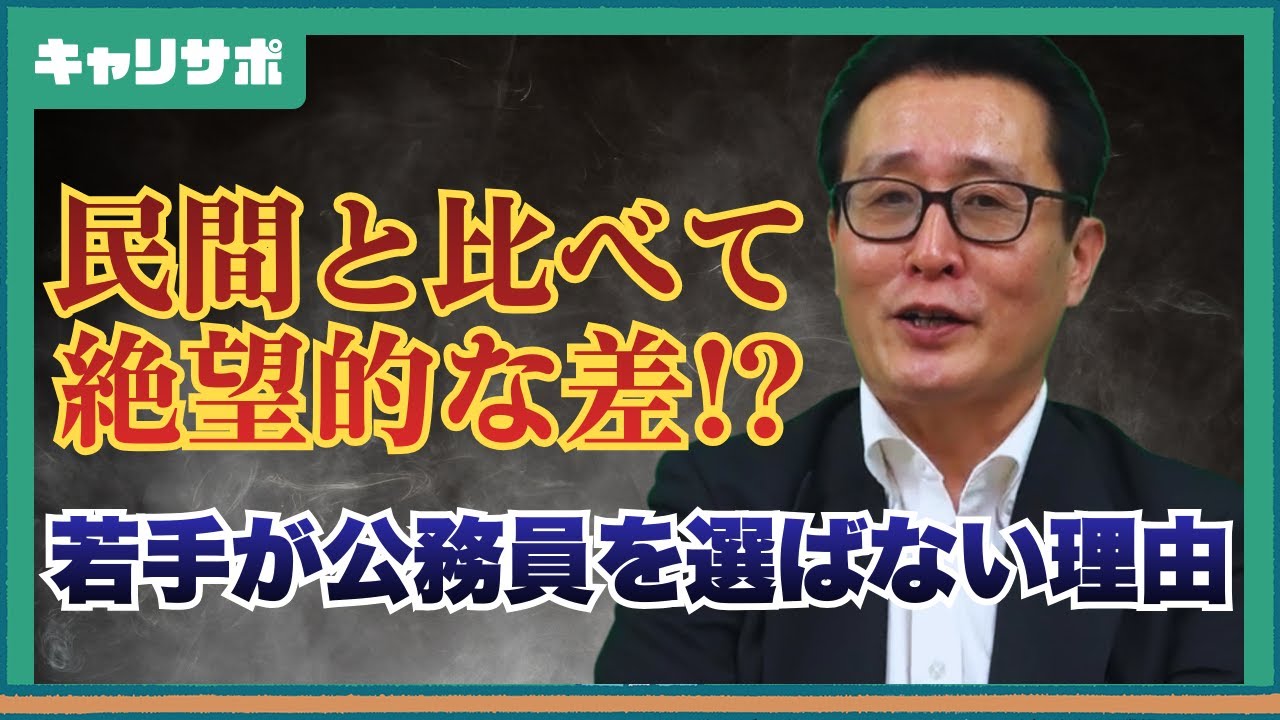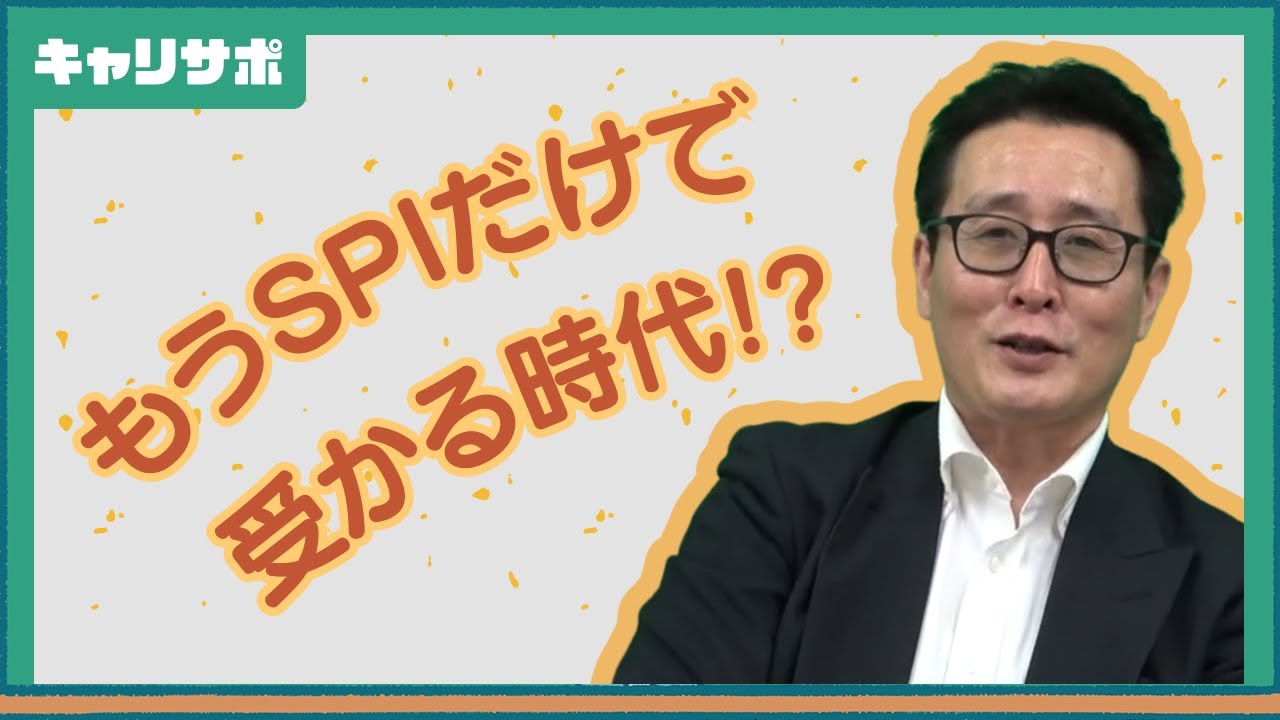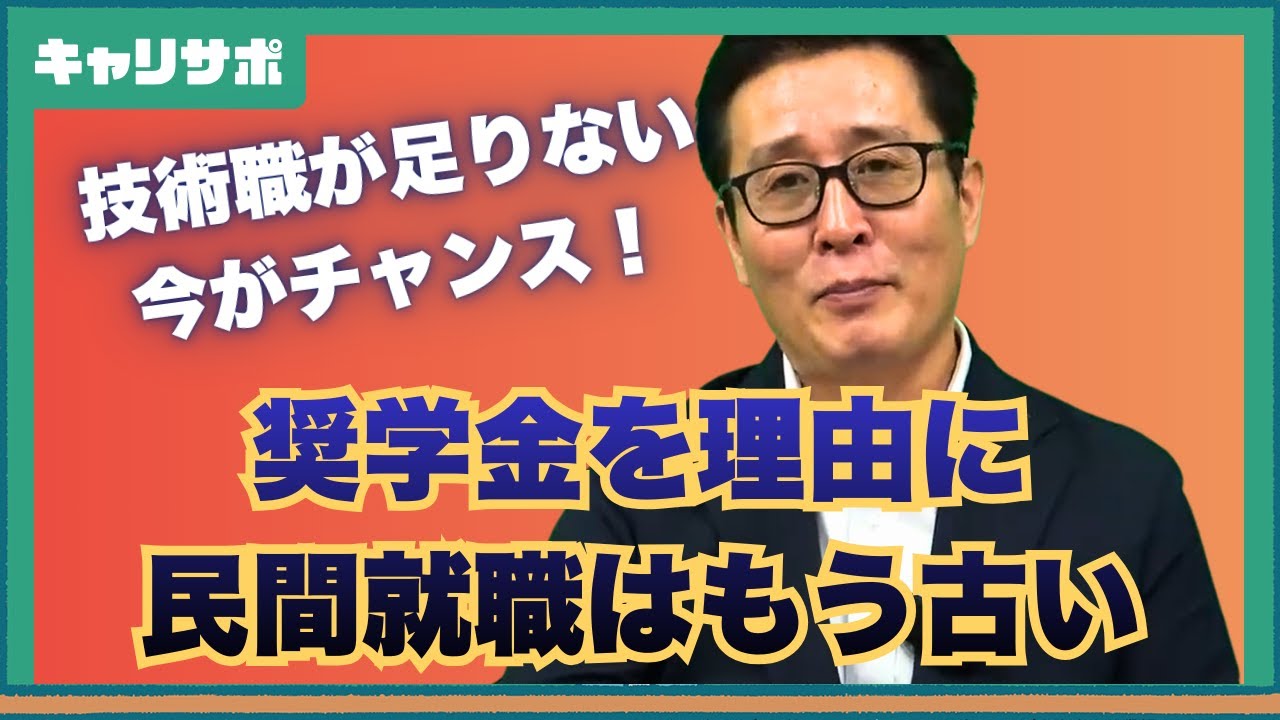【最新版】知らないと落ちる 教養試験の形式&対策まとめ
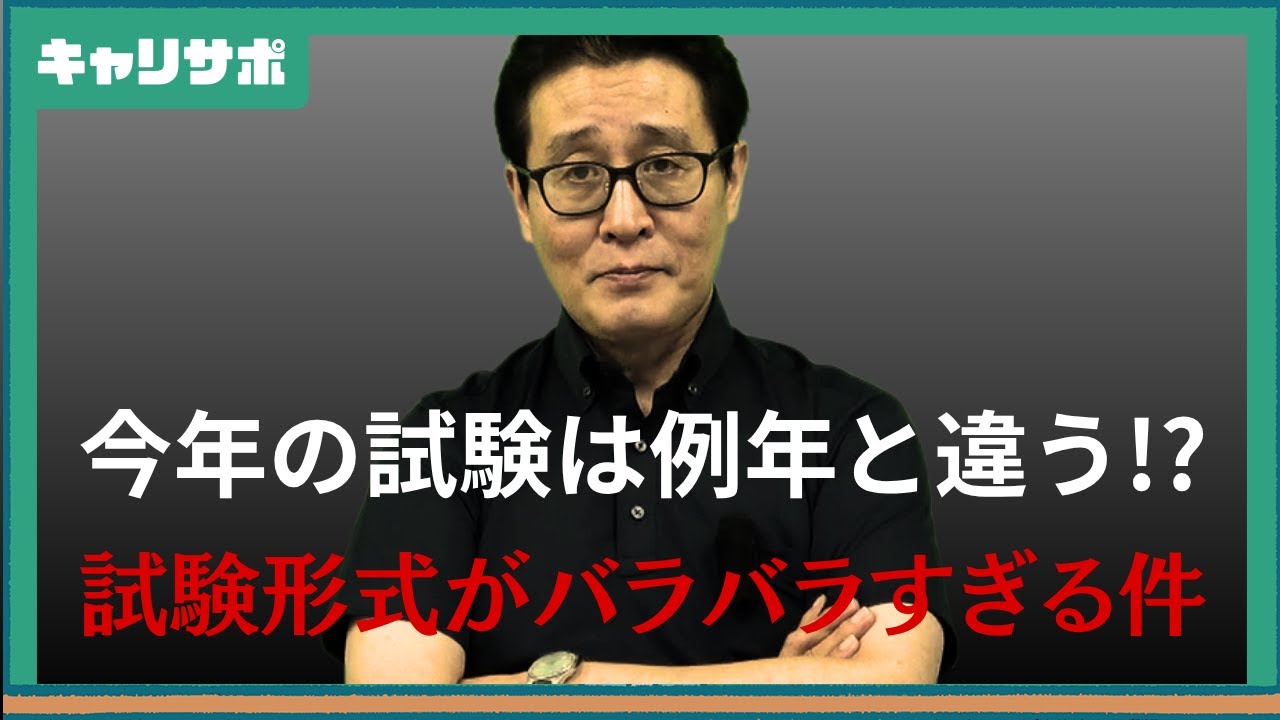
目次
公務員試験の教養試験、最近どう変わってきているのか
最近、「SPIだ」「スコアだ」といった声をよく耳にするようになりましたよね。今年もその流れは大きく変わりつつあります。そこで今回は、公務員試験の中でも特に“教養試験”について、今の傾向や種類、そしてその対策について少しお話ししてみたいと思います。
今は、試験要項に「どんな形式の試験が出るか分からない」という記載があることも増えてきました。なので、少しでもこれからの準備に役立ててもらえたら嬉しいです。
教養試験は、大きく2つに分かれます
まず最初にお伝えしたいのは、教養試験には「独自問題を使うところ」と「共通問題を使うところ」がある、という点です。
独自の問題を作成しているのは、主に国家公務員の試験です。具体的には、総合職・一般職・国家専門職・裁判所事務官・参議院・衆議院・東京都・特別区などが該当します。
こうした試験は、いわゆる“その組織専用の問題”が出されるので、出題傾向が少し特殊だったりします。ただ最近は、出題数が40問から35問に減るなど、少しずつ「軽く」なってきているように感じます。
地方公務員試験は、「共通問題」が主流に
一方で、地方公務員の多く(特に県庁や市役所など)は、「公益財団法人 日本人事試験研究センター」という機関が作る共通問題を使っています。
この試験は、A日程(6月)、B日程(7月)、C日程(9月)と日程ごとに問題が決まっており、全国の自治体が同じタイミングで実施する形です。
このセンターが提供する教養試験には、大きく分けて以下の3つの型があります。
スタンダード型(従来型)
これは、これまでの一般的な公務員試験と似た形式です。
・知識分野20問
・知能分野20問
・合計40問/試験時間:2時間
県庁などでは、今でもこのスタンダード型を採用しているところが多いですね。出題内容は、文章理解・判断推理・数的推理・資料解釈・知識問題(社会、人文、自然、時事)など、いわゆる“王道”の範囲です。
ロジカル型(思考力重視)
こちらは論理的思考力を問う形式です。
・知能分野27問
・知識分野13問
・合計40問/試験時間:2時間
スタンダード型よりも知能問題が増え、知識問題がやや減ります。「数的が得意」「読解が得意」という方には、比較的取り組みやすいかもしれません。一般的には、スタンダード型より少し易しいと言われています。
職務基礎能力試験(BEST)
最近、急に増えてきているのがこの形式です。
・全60問/試験時間:1時間
この形式は「準備いらず」とも言われていますが、まったくの無対策では不安です。とはいえ、実際の問題は比較的易しく、SPIよりも取り組みやすい印象です。
たとえば、「市長・副市長・議長・県議のうち、市民が直接選ぶのは?」といった基本的な知識を問う問題が出題されます。
この形式であれば、ある程度教養がある方なら十分対応できると思います。
SPI(エスピーアイ)の特徴と形式
SPIは、もともと民間企業の採用試験でよく使われていた形式ですが、最近では公務員試験でも取り入れる自治体が増えてきました。
SPIには大きく分けて「言語分野」と「非言語分野」があり、
・言語は、語彙や二語の関係、文章理解など
・非言語は、数的処理の簡易版のようなものです。
SPIには複数の実施形式があるため、少しややこしいかもしれません。
ペーパーテスト(紙ベース)
・言語40問、非言語30問(計70問)
・試験時間:70分
テストセンター(会場のPCで受験)
・問題数は受験者の出来によって変動
・試験時間:35分
Webテスティング/インハウス(自宅受験)
・自宅でPCを使って受験。問題数は人によって異なり、時間も35分ほど。
このように、形式によって多少の違いがあるので、まずは自分が受験する自治体がどの形式を使っているのかを確認することが大切です。
SCOA(スコア)の特徴と対策
スコアも、最近導入が広がっている形式です。
・全120問/試験時間:60分
(短時間でテンポよく解く力が求められます)
出題内容は以下の通りです。
・言語(文章理解・語彙):20問
・数理(計算・方程式など):25問
・論理(推論・空間認識など):25問
・常識(理科・社会):25問
・英語:25問
この形式は「スコアA」と呼ばれています。
また、オンライン受験向けには「スコアI」という形式もあり、こちらは20分で終了します。問題数は変動制で、受験者の出来によって調整される形です。
効率的な学習の進め方
「じゃあ、何から始めればいいの?」という疑問にお答えするなら、まずはSPIの問題集から始めるのがおすすめです。
大体30〜40時間ほど取り組めば、基本的な感覚はつかめると思います。SPIにある程度慣れてきたら、次にスコアの対策をしていきましょう。スコアは理科・社会なども含まれるので、学習の幅が広がります。
実際に今年の合格者を見ても、SPIやスコアでしっかり対策していた人は、やはり強かったです。
目安としては、ある程度評判のいい問題集を3冊、しっかりやりきっていた人は、ほとんど落ちていません。
最後に
最近の公務員試験では、かつて主流だった人文・社会・自然科学を深く掘り下げるスタイルから、徐々に「思考力重視」「スピード重視」へとシフトしてきていると感じます。
「人文科学の時代は、もう終わったのかもしれませんね」と、少し寂しい気もしますが、試験に合格することを最優先に考えるなら、今の形式にしっかり対応するのが賢明です。
ですので、スタンダード型や従来の公務員対策を基本にしつつも、試験直前期には必ずSPIやスコア形式に戻って、スピード感のある演習を行ってください。
そうしないと、実際の試験時間の短さやテンポに、完全にやられてしまう恐れがあります。
これから公務員試験を目指す皆さんにとって、少しでもお役に立てたら幸いです。
応援しています。焦らず、丁寧に、一歩ずつ準備を進めていきましょう。
この記事の動画はこちら↓