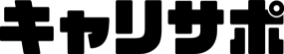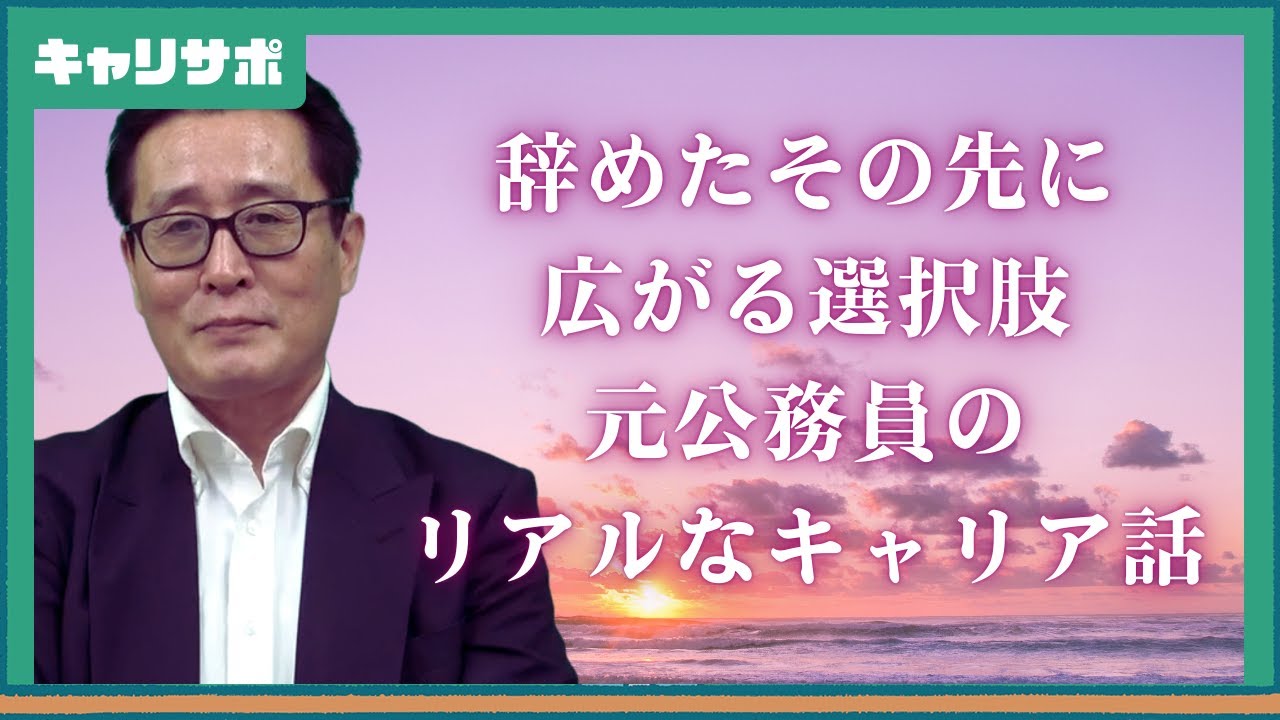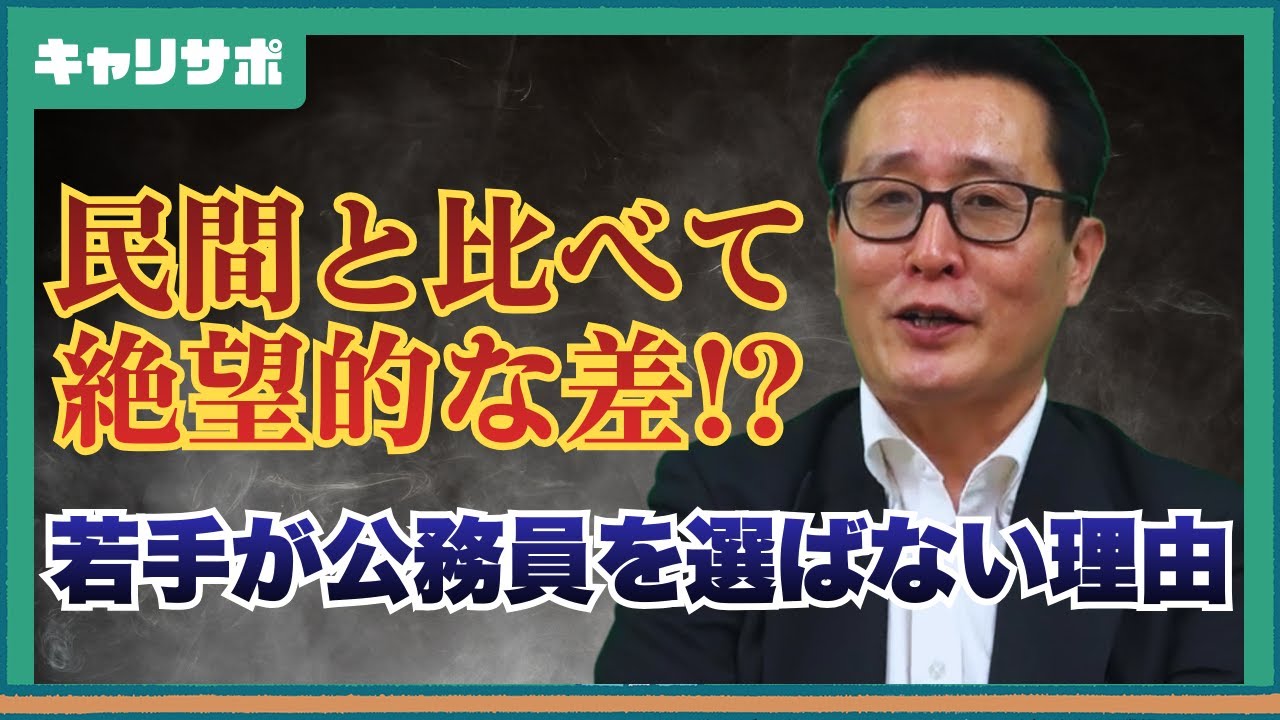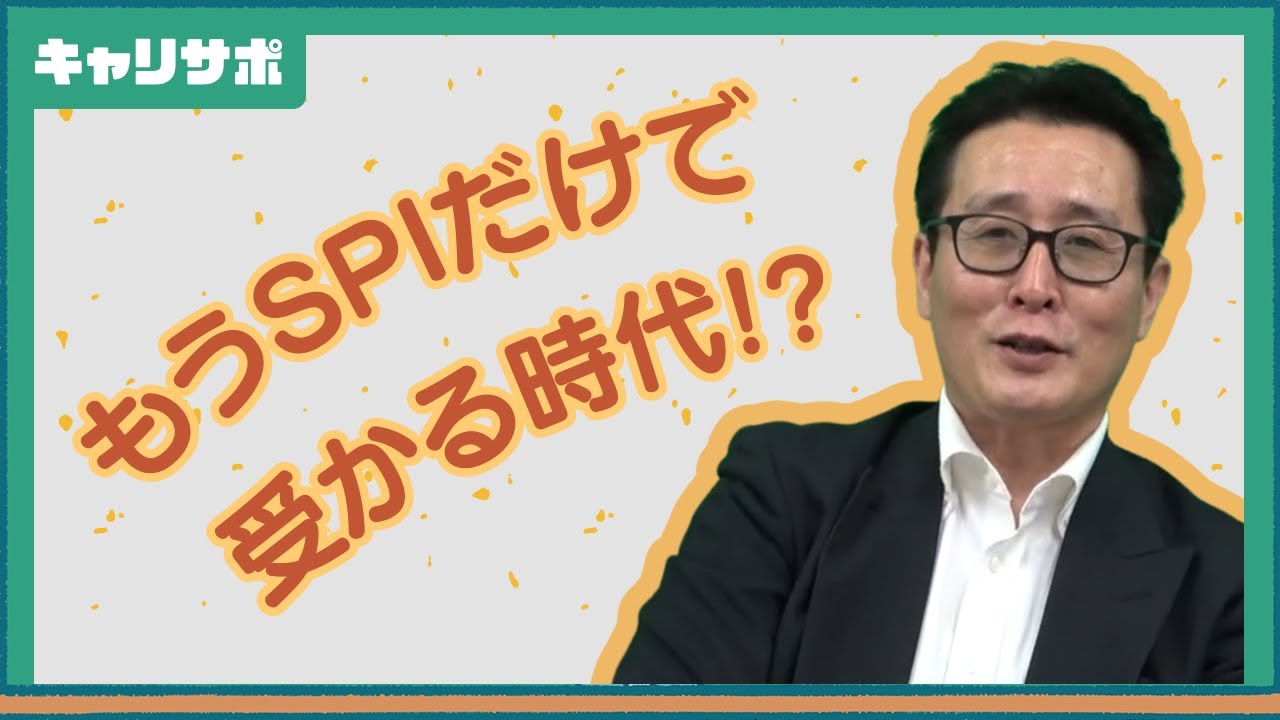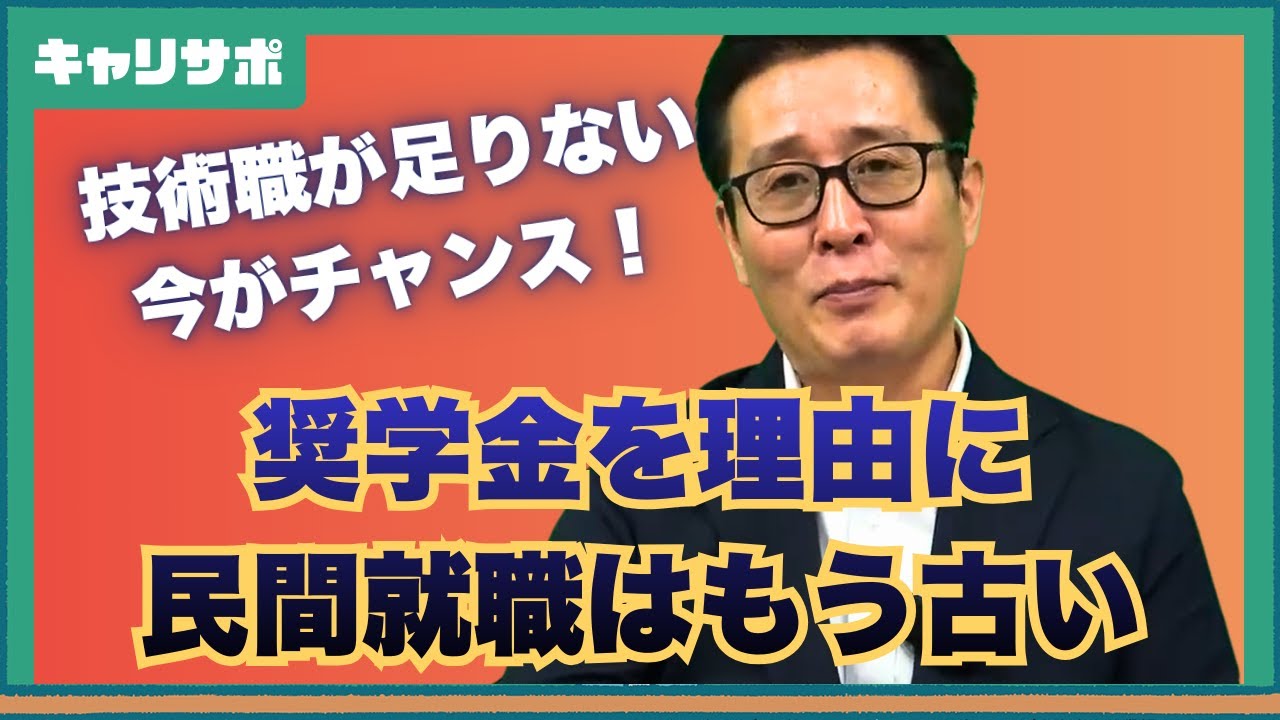【公務員試験】公務員試験の合格基準とは?ボーダーと採点の仕組みを徹底解説
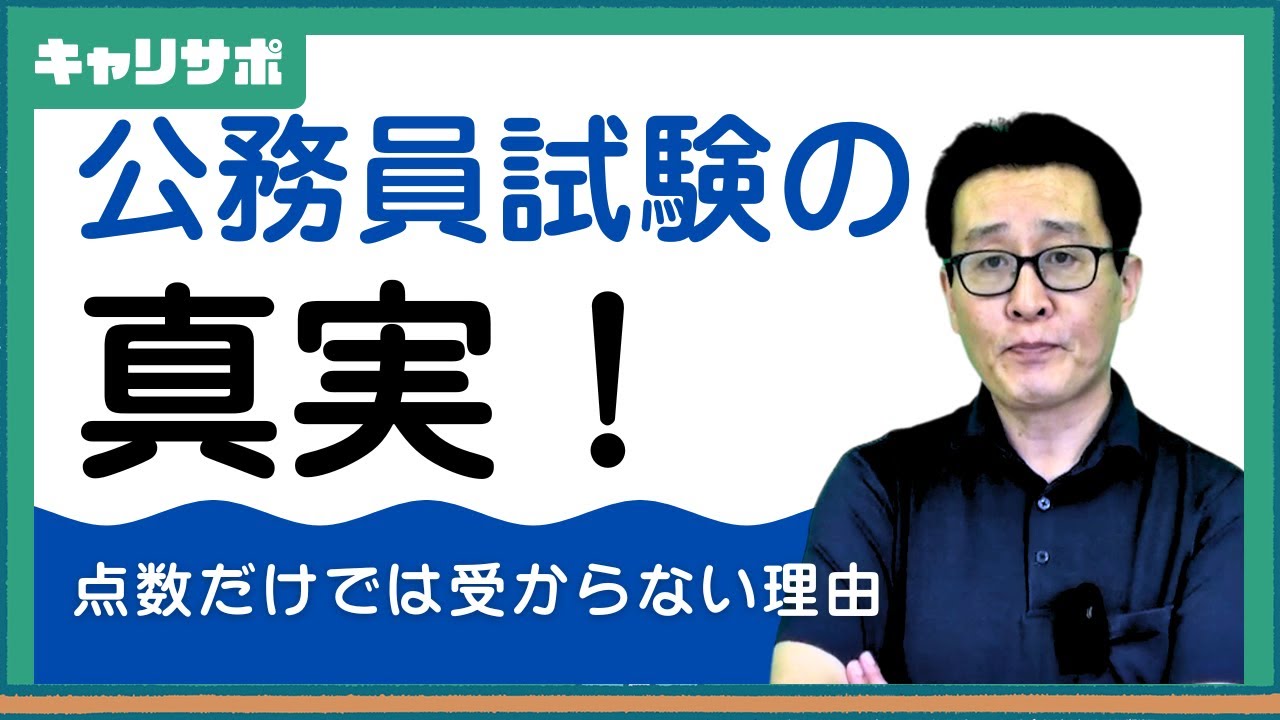
今回は、昨年の公務員試験のボーダー点について、まとめてご紹介します。
また、合わせて「採点の仕組み」についても、解説していこうと思います。
目次
素点で決まるものではない
「ボーダー点」は単に素点(実際の得点)で決まるものではありません。よく「配点比率をそのまま掛けて計算する」と思っている方もいますが、それでは誤差が大きくなってしまい、実際の合否とはズレてしまいます。
正確に理解していただくためにも、ここではまずその仕組みをご説明します!
標準点について
択一試験の評価は、「標準点」という形式で評価されます。これはイメージとしては「偏差値」に近い考え方で、得点をそのまま比べるのではなく、全体で自分がどの位置にいるかを示しています。そのうえで、配点割合を掛けて計算していく・・・という形になります。
なので、単に「〇〇点取りました」と言われても、それがどの程度なのかは、標準点に直してみないと分かりません。
試験ごとに配点は異なる
試験ごとに配点の割合も違ってきます。たとえば、国家一般職(行政)であれば、基礎能力試験:専門試験:一般論文:人物試験の配点は「1:1:1:2」です。
一方で国税専門官は、基礎能力:専門試験:人物試験が「3:3:3」となっており、人物試験のウェイトが昨年まで「2」だったところが「3」に引き上げられています。
基準点について
「基準点」、いわゆる「足切りライン」も重要です。これは、一定の点数を下回ると、それだけで不合格になってしまうというものです。一般的には、満点の30%程度が一つの目安とされています。つまり、どんなに他で点数が取れていたとしても、この基準点を下回ると、それだけでアウトです…。
注意点
「一次試験に通った」と思っていても、実際は論文などの評価によって最終的には不合格となってしまうケースもあるので、注意してください!特に論文の準備はしっかりしておきましょう。とはいえ、論文も偏差値評価ですので、普通に書ければそこまで問題はありません。
最終合格者の決定について
一次試験を通過した後に、論文と面接の評価が加わり、そこで最終合格者が決まります。
国家一般職の面接試験の評価は「A・B・C・D・E」の5段階ですが、「D」評価でも合格できることがあります。一方で、国税専門官では「A・B・C」評価までが合格対象で、「D・E」は不合格となります。
なぜ職種で合格対象が違うのか
それぞれの職種で求められている人材像によって、合格対象は異なります。幅広い業務がある国家一般職では多様な人材が求められますが、国税専門官の場合は業務内容がある程度決まっており、少し基準が絞られていると考えられます。
まとめ
公務員試験では「合格を目指す」というよりも、「不合格にならないようにする」という姿勢が大切です。せっかく択一試験で満点を取っても、面接や論文で基準点を下回れば、それだけで不合格になってしまいます。
試験の合格の仕組みをしっかり理解したうえで、自分に合った対策を行っていくことが、合格への近道になると思います。
キャリサポには、志望自治体の試験に対して、受講生一人ひとりがどういった対策をとればいいか一緒に考えるサポート体制があります。受講を検討している方は、ぜひご相談ください。
今回のブログの内容の動画はこちら↓