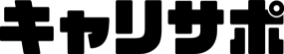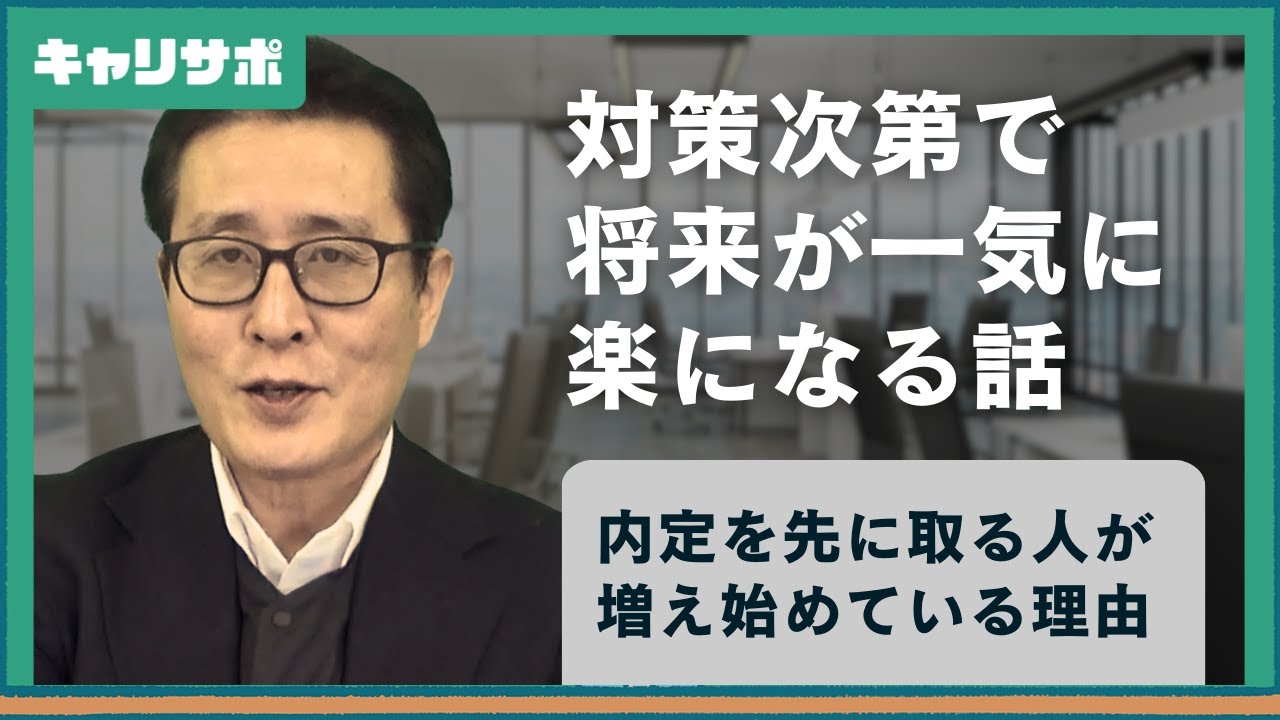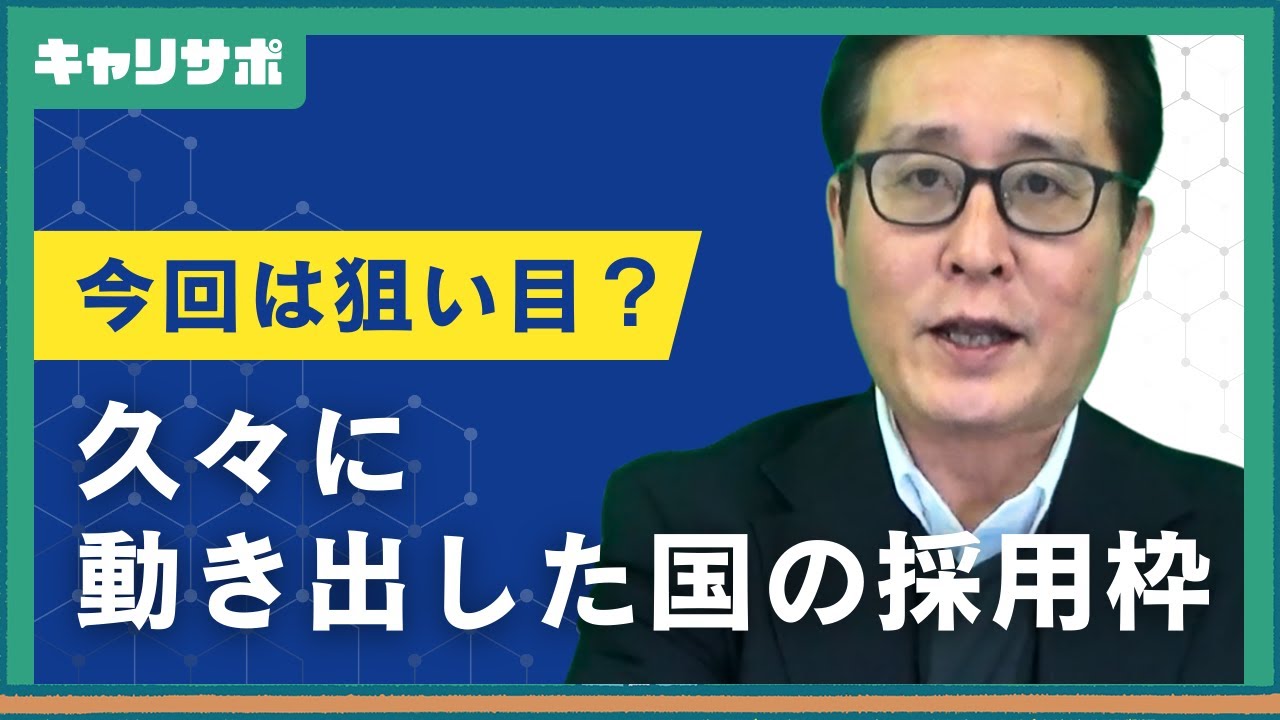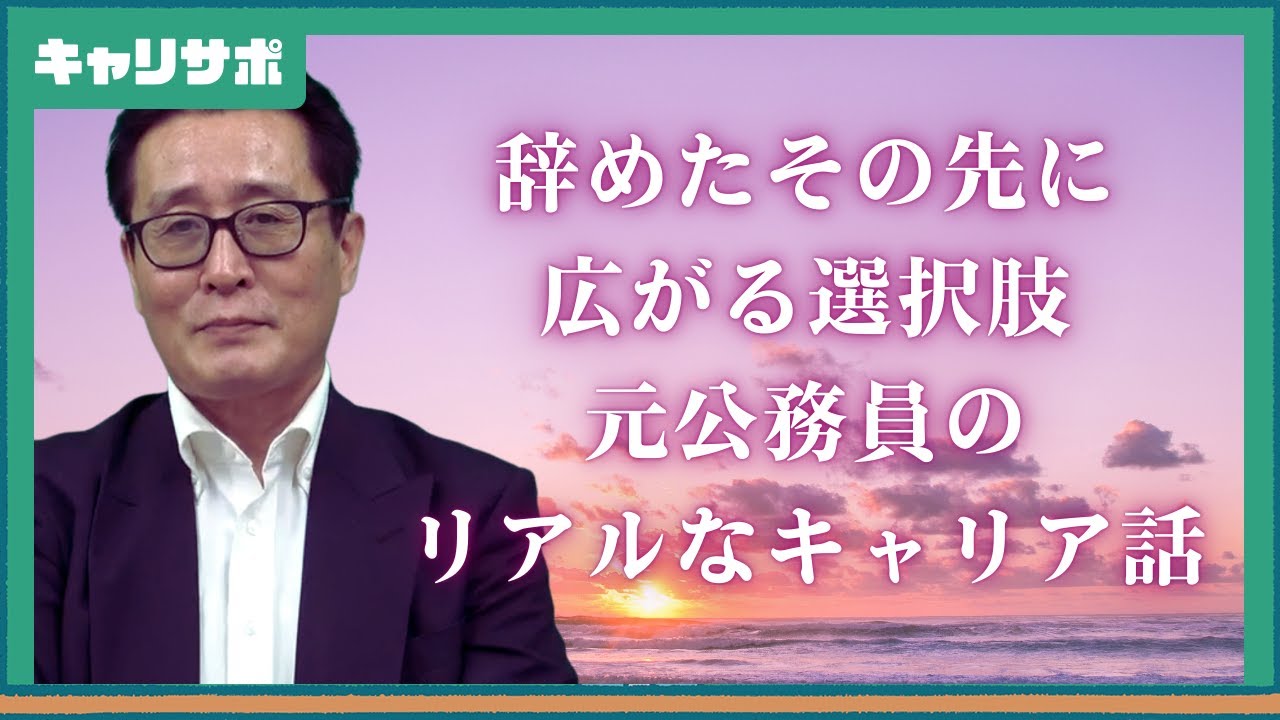【公務員試験】公務員試験が超簡単に!?点数の推移で徹底解説
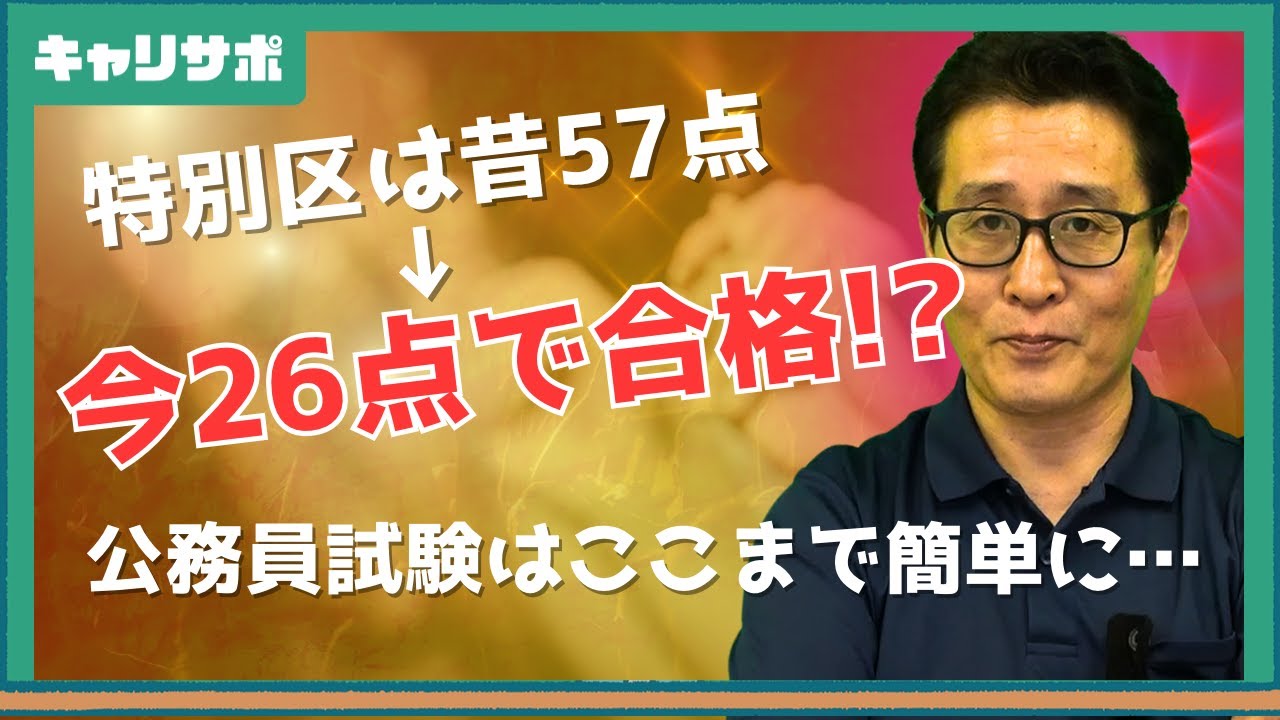
今回は、「公務員試験は簡単になっている」というテーマでお話しします。
昔のものと比べて、どのくらい簡単になったのか見ていきましょう。
目次
昔の公務員試験と比べて、簡単になった??
多くの試験で試験制度が大きく変わりましたが、今回は比較しやすい特別区をサンプルとして取り上げます。特別区ではSPIの試験が導入されましたが、専門科目と教養科目の試験内容自体は変わっていないので、比較には適しています。
試験内容は教養40点、専門40点の合計80点満点で、択一式です。教養論文なども含まれますが、今回は択一式の点数だけで比較します。
少し古いデータですが、平成16年と平成17年の特別区の合格ラインをデータから見ていきます。
(これは特別区が公表しているものではなく、私が受験生の自己採点から合否を判断して算出したデータなので、あくまで目安として捉えてください。)
平成16年は80点中55点、平成17年は57点が合格ラインでした。このあたりがピークで、その前は60点あったように記憶しています。私の手持ちデータでは、この57点が最高点です。
その後、平成18年には50点に下がり、19年が52点、20年が51点と推移し、現在はなんと26点まで下がっています。特別区は基本的に合格点を公表していませんが、足切り点が存在すると考えられています。過去のデータから推測すると、おおよそ3割程度が足切り点だろうと予想できます。これは、教養と専門がそれぞれ12問正解で、合計24点くらいが足切り点にあたるのではないでしょうか。つまり、今はその足切り点でも受かってしまう可能性があるのです。昔の57点で合格した人からすれば驚きかもしれませんね。
特別区職員の声は・・?
先日、OBの方々とお話しした時に「お前ら、今特別区は何点ぐらいで受かってると思う?」と聞いたら、「50点くらいですかね?」と答えていました。私が「いやいや、24点だよ」と教えたら、とても驚いていました。職場の特別区職員も皆驚いていると聞きます。それぐらい簡単になったということですね。
昔と比べて簡単になった!
冷静に考えてみれば、教養は40点中12点です。そんなに大変ではありません。特別区の教養試験は数的処理が19問、文章理解が4、5問出題されるので、数的処理で10点、文章理解で4、5点取れば、あとは知識で2点取れば十分に合格ラインに達します。
専門試験も、11科目から5問ずつ、合計55問出題されます。1科目あたり1点か2点取れば合格できるのです。つまり、専門科目を全て完璧にやる必要はありません。昔のように経済や民法を徹底的に勉強するのではなく、出題傾向を見て1点、2点取れるレベルで勉強すれば合格できるため、非常におすすめです。
今後、公務員が人気になる可能性
個人的な見解ですが、トランプ政権の関税問題が始まった時、日本の自民党が大敗しましたよね。もし政治空白が生まれ、高率の関税が課せられた場合、就職に大きな影響が出てくる可能性があります。そうなると、公務員を目指す人が増えるでしょう。
過去のリーマンショックの時も、民間企業が厳しくなり、公務員を目指す人が一気に増えました。もしそのような状況になれば、公務員を目指す層の中でも、特にSPIや教養科目から受験する人たちが増えるでしょう。
ですから、この状況を鑑みて、今からでも公務員を目指すことを強くお勧めします。
専門科目に手をつまだ時間がありますし、公務員試験は全てを完璧にやる必要はありません。非常に合格率が高いゾーンを狙って、効率的に勉強を進めていきましょう。
今回のブログの内容の動画はこちら↓