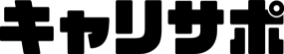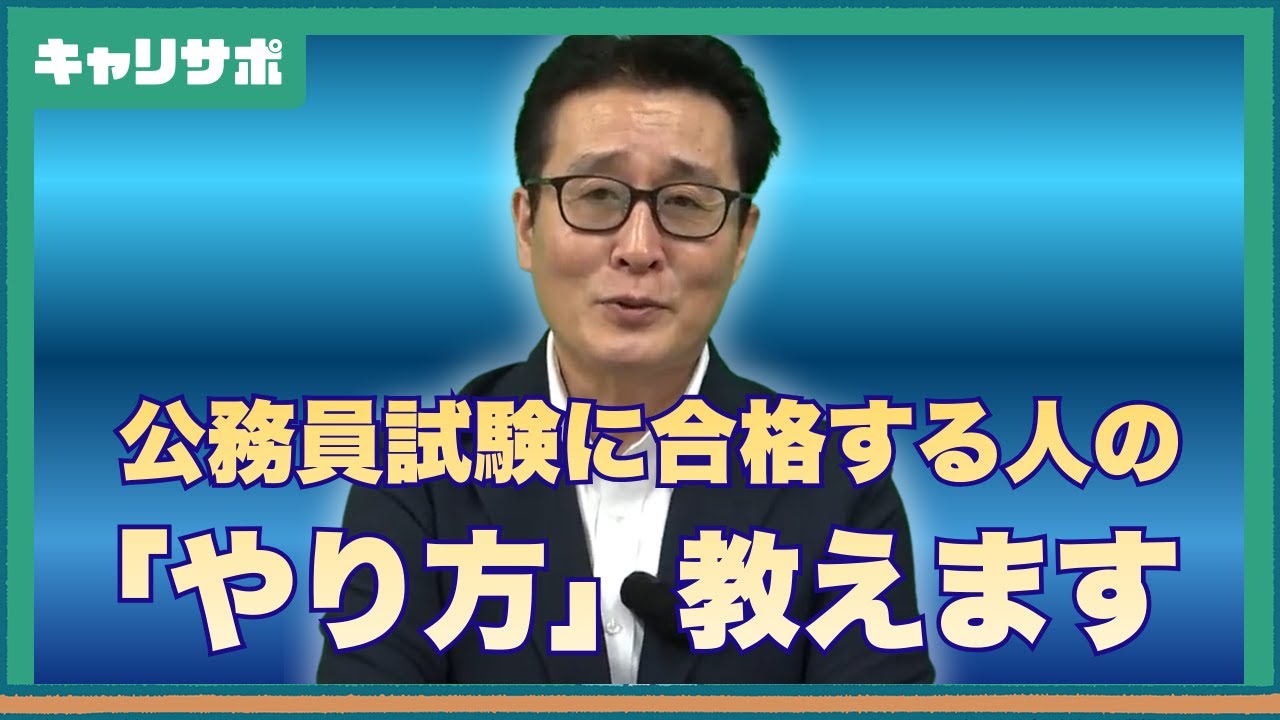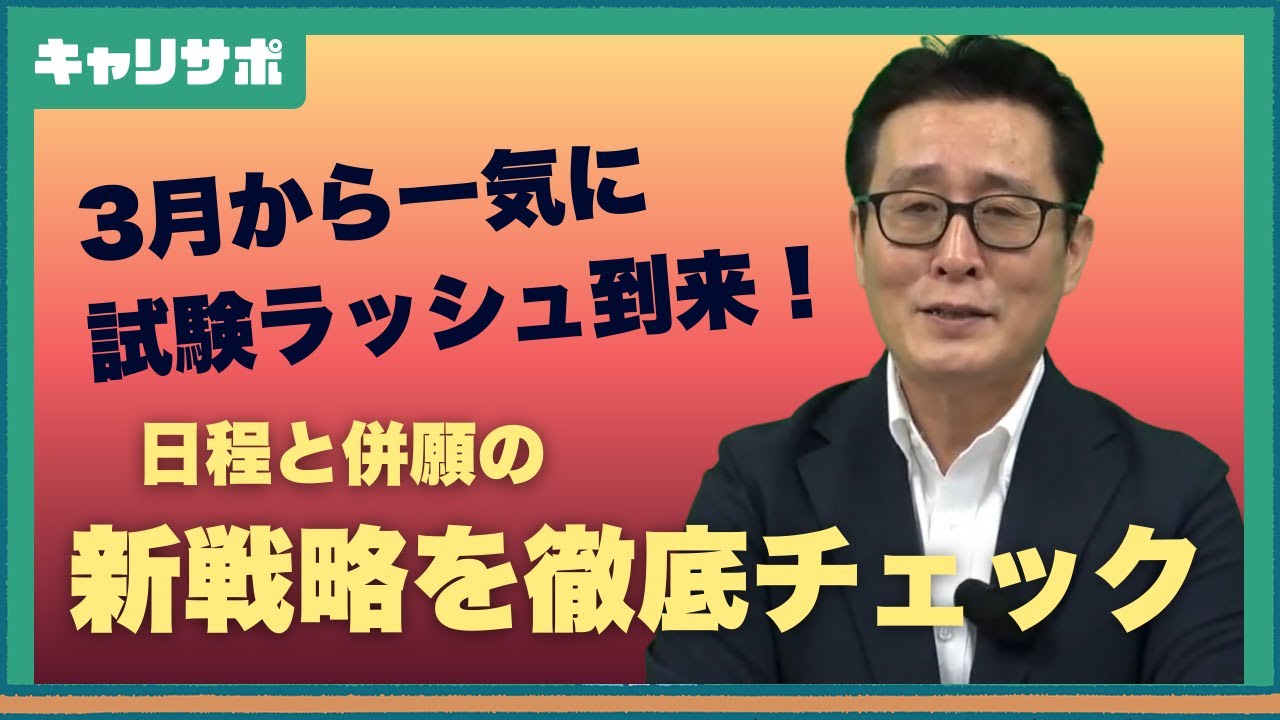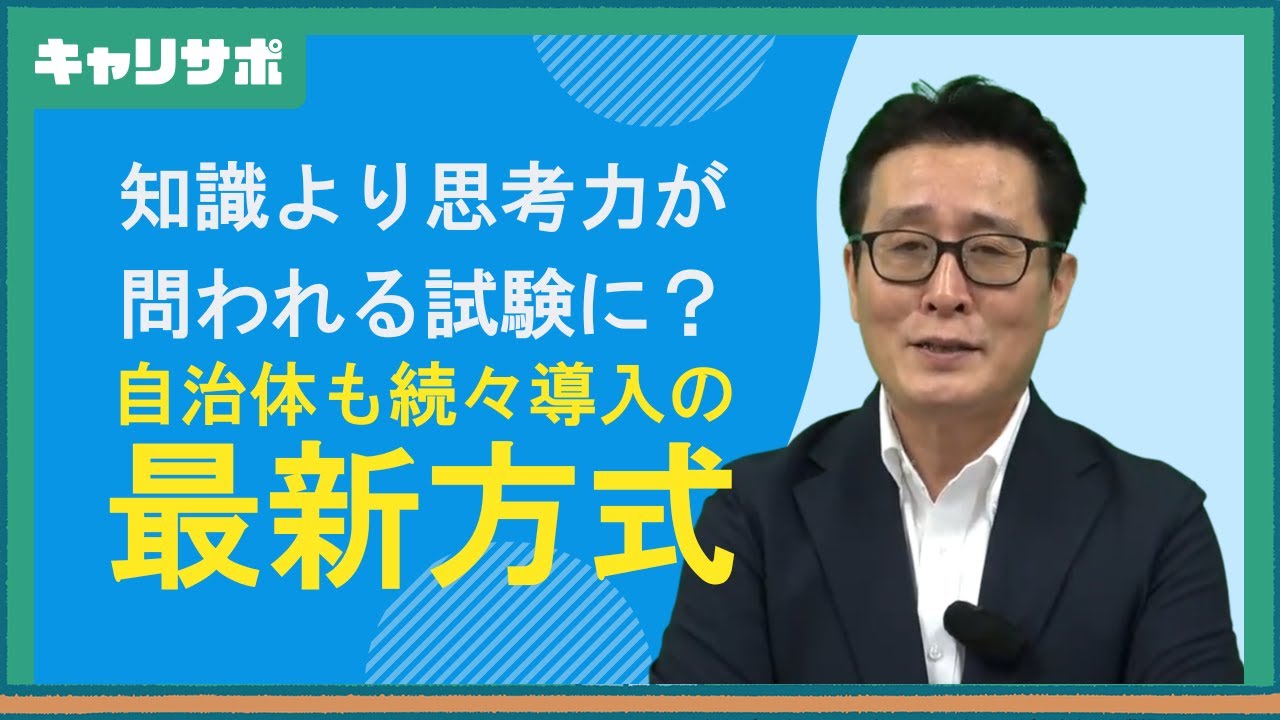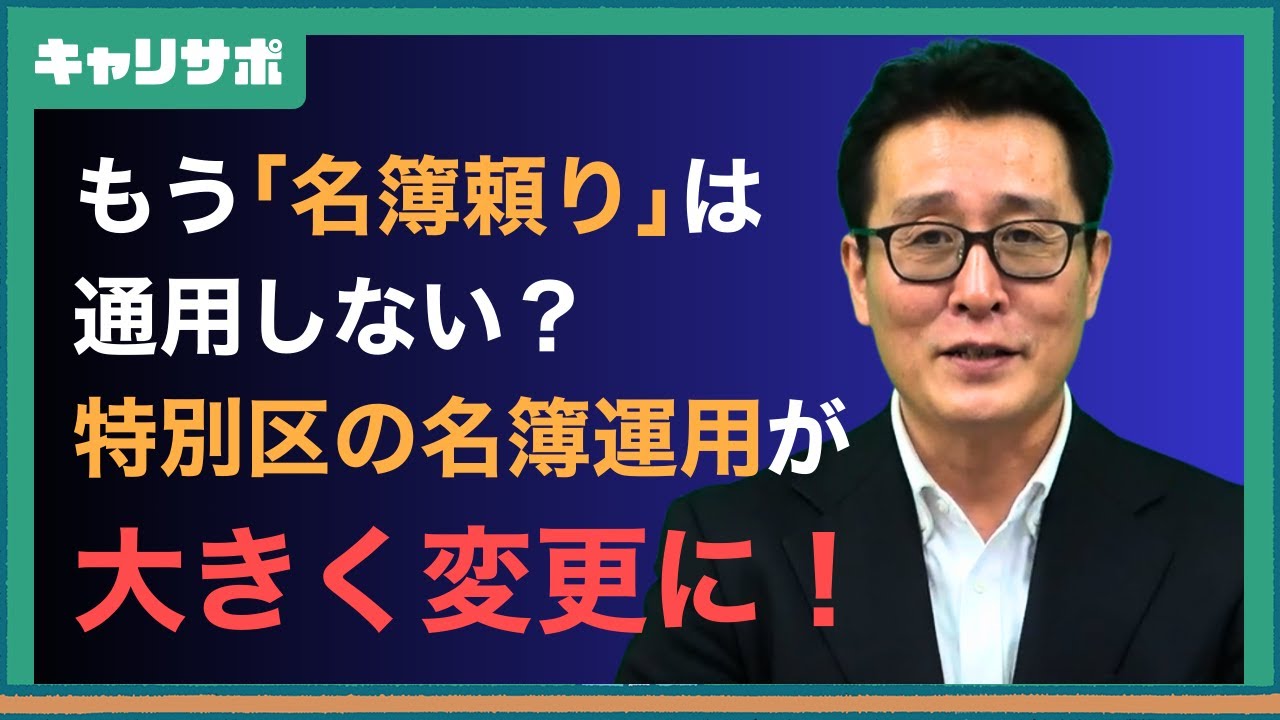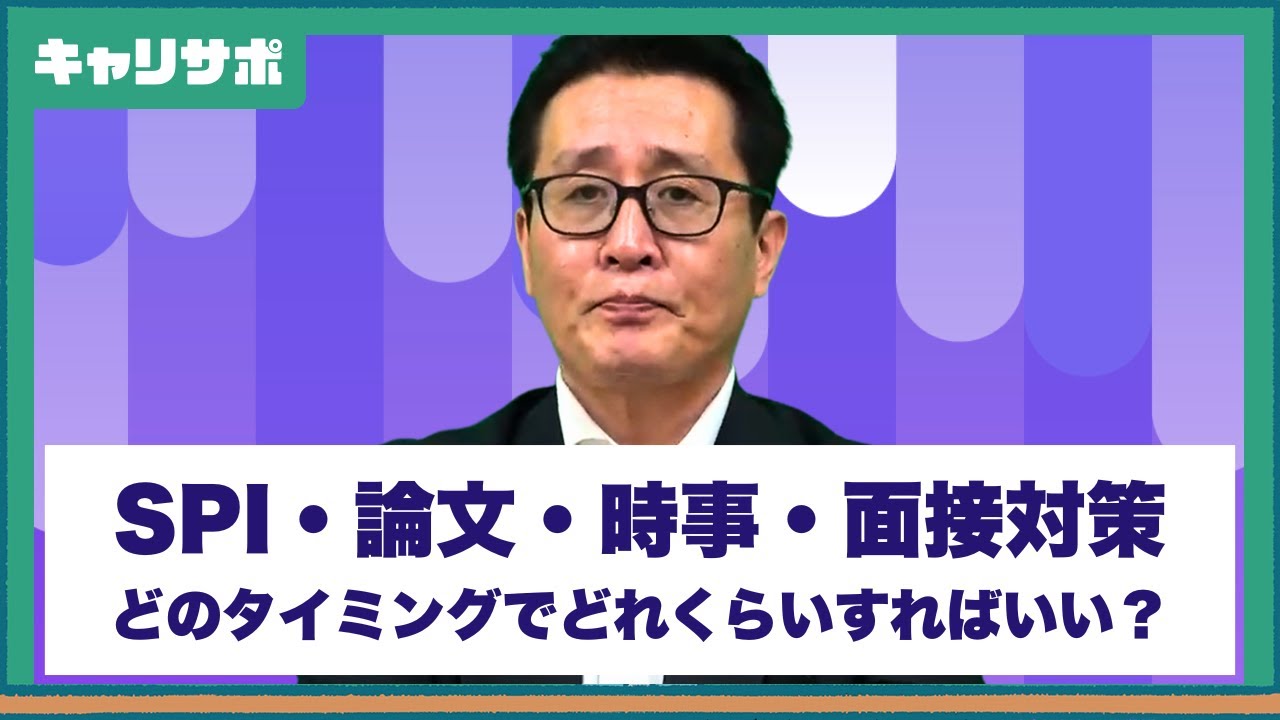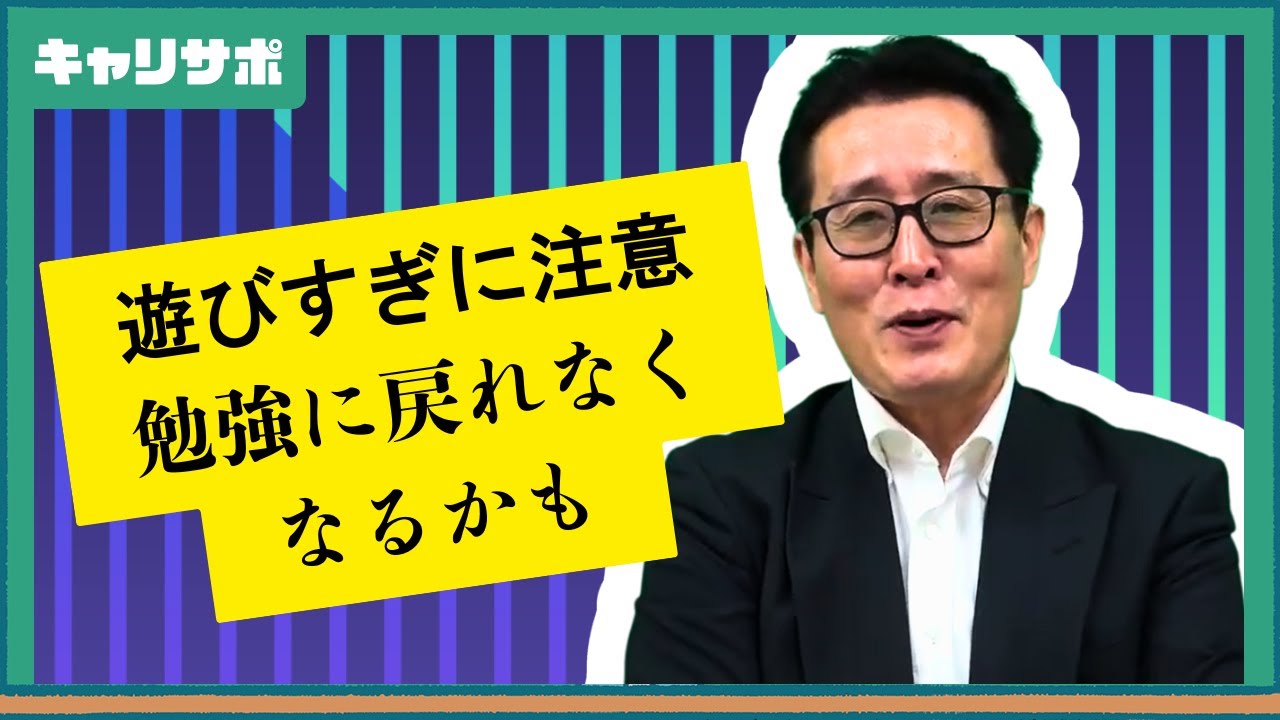【合格者が実践】試験情報の収集法と説明会活用のコツ

公務員試験対策といえば、教養科目や専門科目の勉強、面接練習などが真っ先に思い浮かびます。
しかし、実は「試験情報の収集」も合格のために欠かせない戦略の一つです。
近年は、自治体による試験日程の前倒しやSPIの導入など、公務員試験の形が大きく変化しています。
こうした動きに取り残されないためには、最新情報をいかに早くキャッチできるかが鍵になります。
今回は、キャリサポの卒業生が合格までに実践した情報収集法を紹介します。
目次
1. 公式サイトを「定期チェック」する
まず基本は、志望する自治体の公式ホームページを定期的に確認することです。特に募集要項や採用ページはブックマークし、更新情報を見逃さないようにしていました。
ただし、公式ページが必ずしもリアルタイムで更新されるとは限りません。昨年度の試験日程や実施要項を事前にチェックして、例年の流れや準備期間を把握しておくことも重要です。
2. SNSを情報アンテナに活用
最近は、公式X(旧Twitter)やInstagramで採用情報を発信する自治体が増えています。私は通知設定をオンにし、勉強の合間にこまめに情報収集していました。
SNSは公式サイトよりも早く最新情報が出ることもあるので、見逃せない情報源です。
3. 合同説明会・オンライン説明会の活用
複数の自治体が参加する合同説明会や、オンライン開催の説明会は、短時間で多くの情報を集められるため効率的です。私は本命以外の自治体でも積極的に参加し、試験の傾向や求める人物像を比較していました。
ただし、気軽に参加できる分、集中力が途切れやすいので、必ず配布資料を入手し、必要なことはメモを取ることを習慣にしていました。
4. 職場体験・インターンで現場を知る
志望度が高い自治体が職場体験やインターンを実施しているなら、ぜひ参加することをおすすめします。現場の雰囲気を直接感じられるだけでなく、「ここで働きたい!」というモチベーションが高まり、学習にも良い影響を与えます。
5. 予備校・仲間・先輩からのリアルな情報
私が通っていたキャリサポでは、同じ目標を持つ仲間同士で試験情報を共有できる環境がありました。
さらに、試験を突破した先輩方からは、受験のリアルな体験談や最新の出題傾向を聞くことができ、とても参考になりました。
また、経験豊富な講師陣からは、最新情報や傾向分析を得られたことが大きな武器となりました。
まとめ
公務員試験は、勉強の努力だけでなく、情報戦でも差がつきます。SNSや説明会、インターン、予備校など、多様な手段を駆使して最新情報を集めることで、他の受験生に一歩先んじることができます。
皆さんも、自分に合った情報収集スタイルを確立し、試験突破に向けて有利なポジションを確保しましょう!