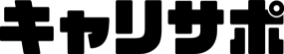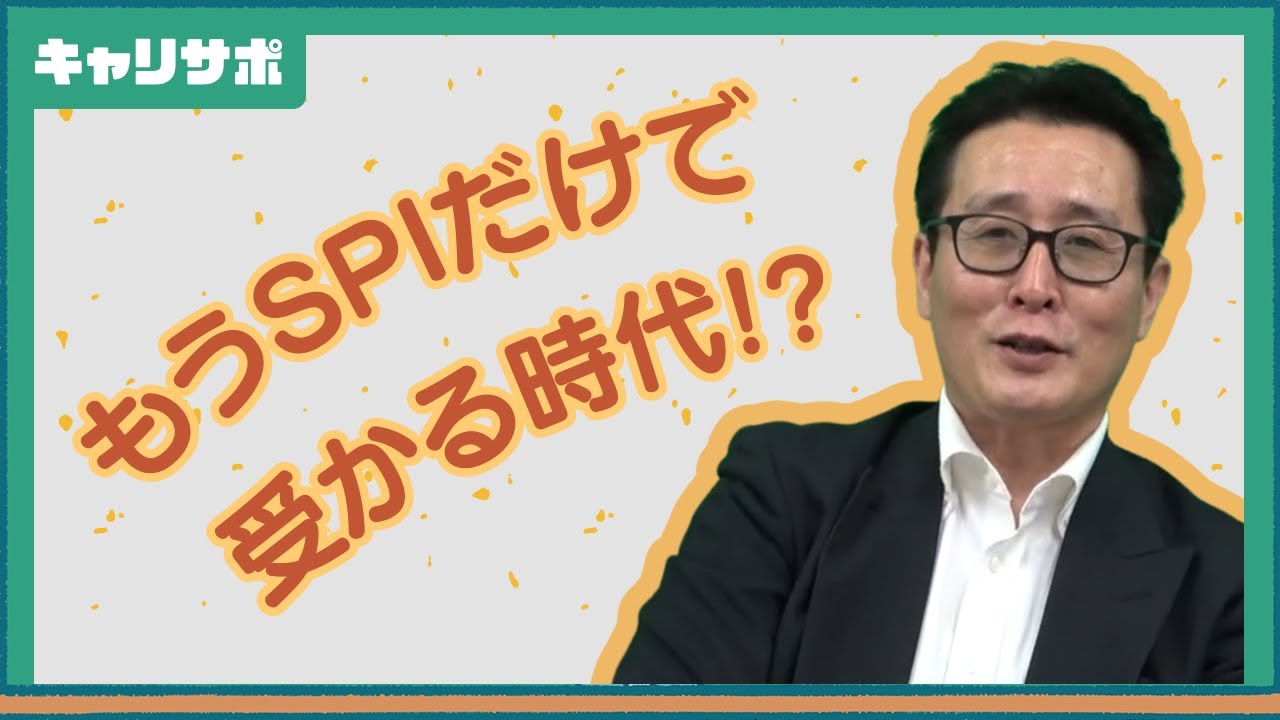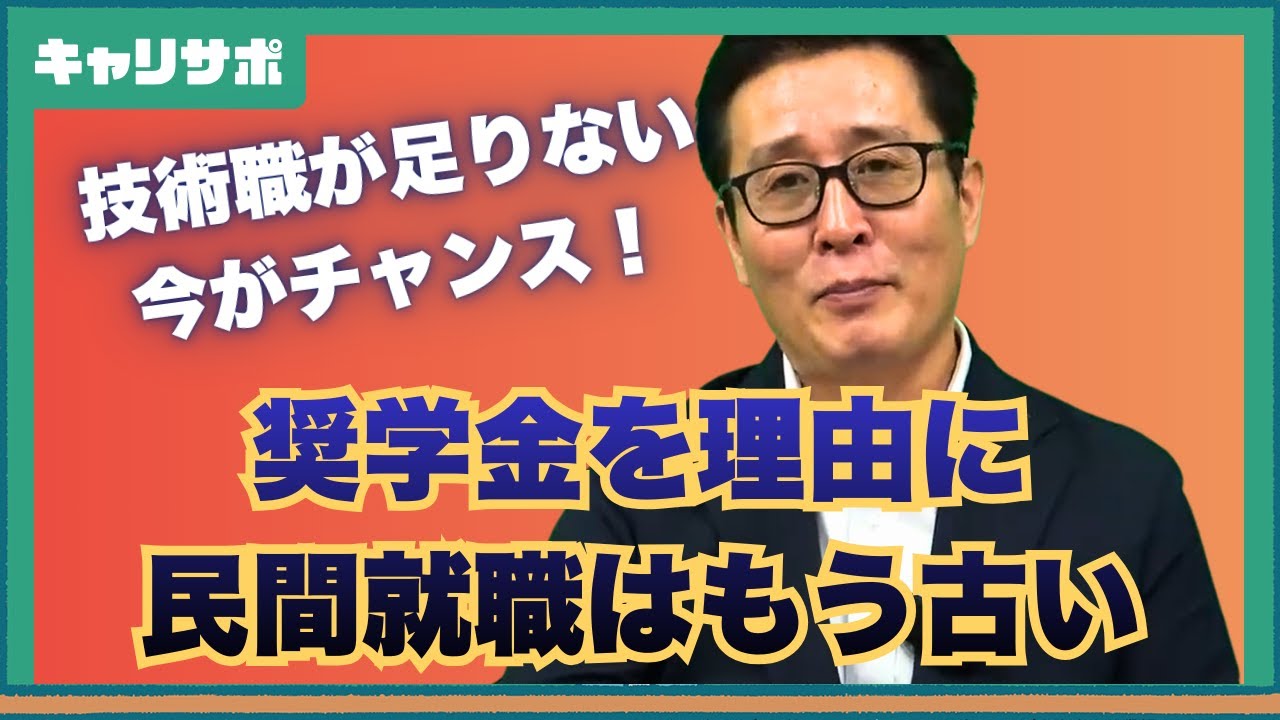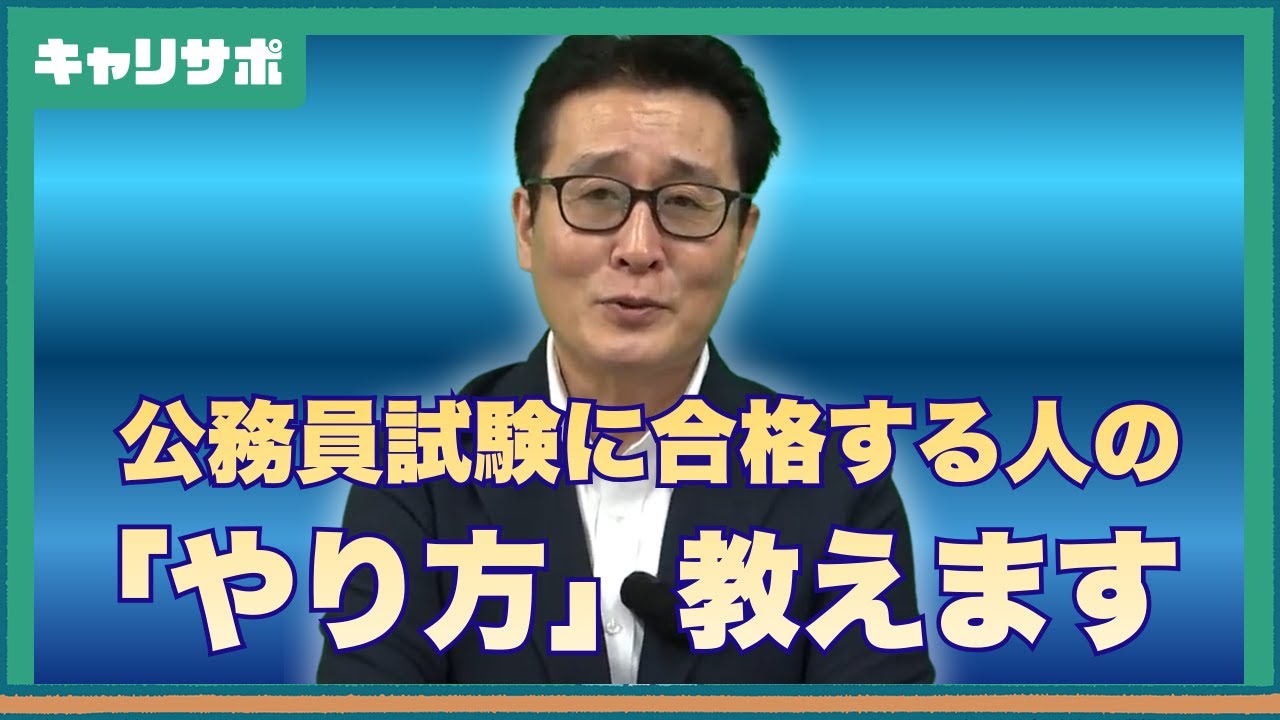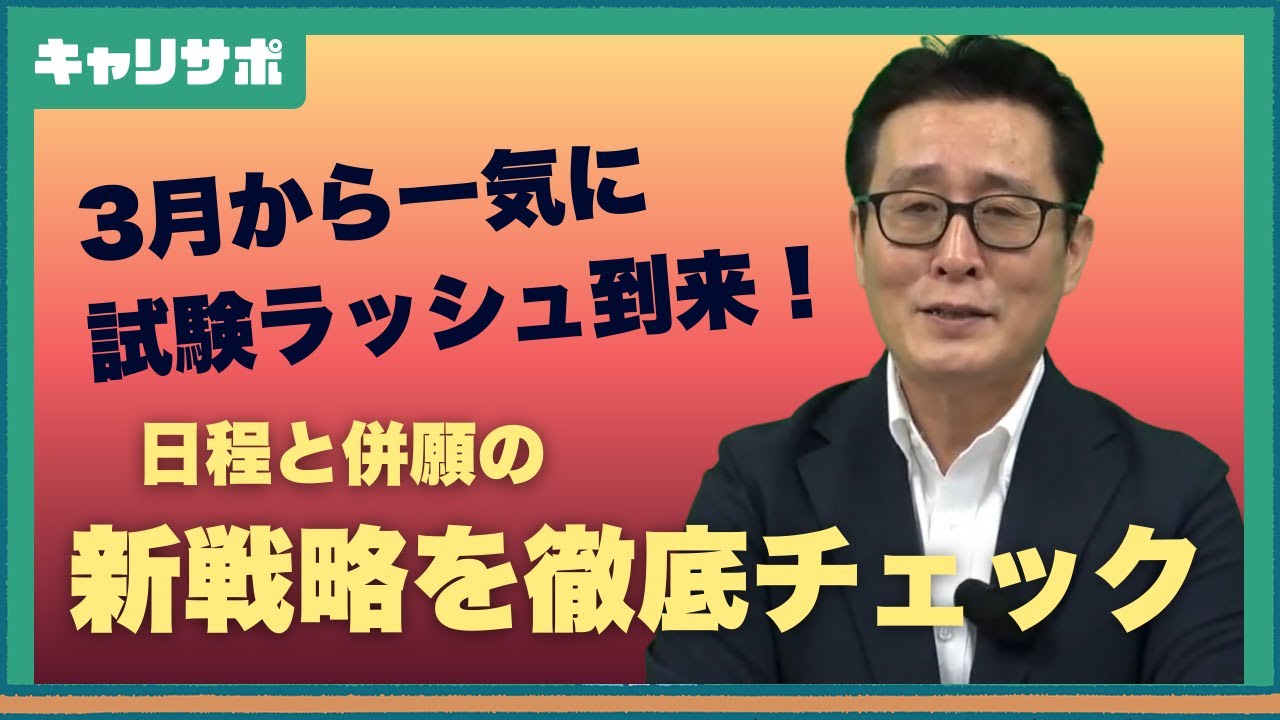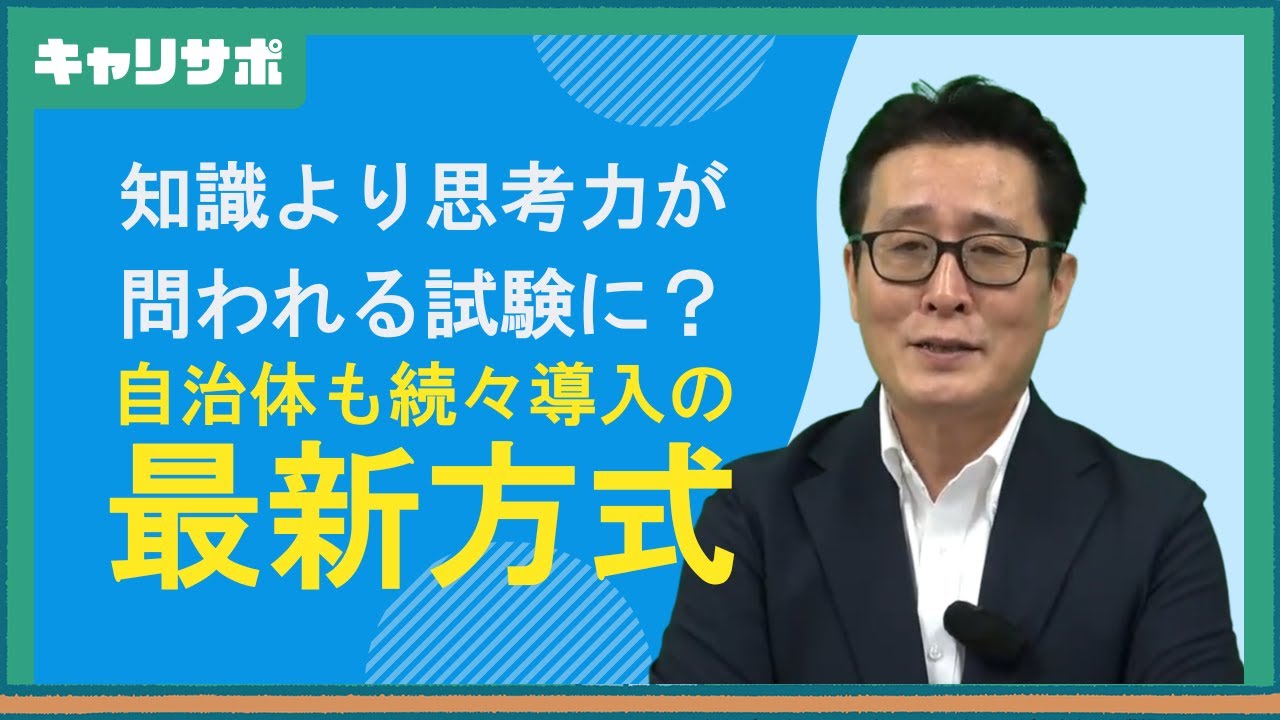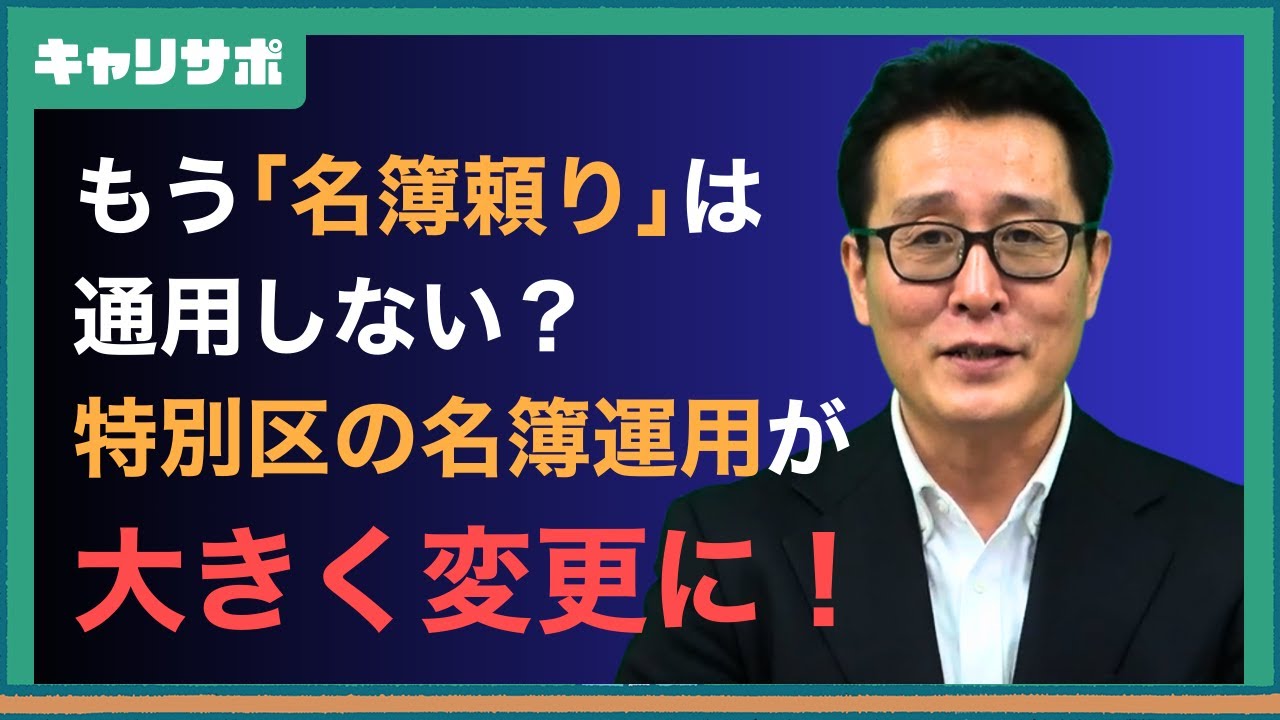国立大学法人試験が変わる!年齢上限引き上げ&試験内容も再編

今回は、令和8年度から大きく変わる「国立大学法人職員統一採用試験」について、私たちなりに分かりやすくまとめてみました。国立大学法人を目指している方は、ぜひチェックしてみてください。
目次
■ 国立大学法人職員とは?
少しだけおさらいをしておくと、国立大学の職員は昔は国家公務員(一般職)として文部科学省の管轄にありました。しかし大学の法人化によって独自の採用ルートができ、現在は「公務員に近いけれど、厳密にはちょっと違う」立場になっています。
とはいえ、公務員試験の勉強をしている方にとってはかなり受けやすい試験で、学習内容の多くがそのまま活かせます。
個人的には、公務員志望の方が“併願先のひとつ”として考えるのにぴったりだと感じています。
■ 受験者が年々減っている?
国立大学法人職員試験は、ここ数年で受験者数が大きく減っています。
・令和3年度:8,281人
・令和4年度:8,031人
・令和5年度:6,655人
・令和6年度:5,198人
4年で約3,000人の減少です。こうした状況も、今回の制度変更につながったのだろうと感じます。
■ どこが変わるのか?(令和8年度以降)
① 年齢制限が「30歳 → 35歳」に拡大
受験可能年齢が 「30歳 → 35歳」 に拡大されました。
社会人経験を持つ方も受験しやすくなります。
② 一次試験(教養試験)の構成が大きく変化
これまでの教養試験は 知識20問 × 知能20問 の合計40問でしたが、配分が次のように変わります。
【変更前】
・知識分野:20問
社会科学7、人文科学7、自然科学6
・知能分野:20問
文章理解7、判断推理8、数的処理(数的推理+資料解釈)5
【変更後】
・知識分野:13問(7問減)
自然・社会・人文に関する一般的な内容
※自然科学は分量減。ただし時事的・トピック的内容が増える可能性あり
・知能分野:27問(7問増)
文章理解:9問(+2)
判断推理・数的推理:15問
資料解釈:3問
※合計で数的処理は5問増
全体の問題数は変わらないのに、「知識かなり減ったな…」「そのぶん思考系の問題が増えたな…」という印象です。
特に数的処理が5問増えるのは、苦手な人にとっては少し大変かもしれません。逆に言えば、数的・判断が得意な人はより有利になりそうです。
■ 勉強のポイントは?
・自然科学が減るので、理科に不安がある人には朗報
・一方、数的推理や判断推理は避けて通れない
・社会・人文は公務員試験の一般教養レベルで対応可能
SPI中心で勉強している方はやや厳しい可能性がありますが、公務員試験対策をしている方なら、比較的スムーズに移行できると思います。
■ 国立大学法人職員のリアル
卒業生からもいろいろな相談を受けていますが、国立大学法人は総じて「働きやすい」という声が多いです。
・ワークライフバランスが良い
・大学の研究環境に触れられる
・大学によっては国際的な学会やイベントに関わる機会がある
もちろん、人間関係が合わずに辞める人もいますが、それはどの職場でも同じこと。
全体としては、落ち着いて長く働ける環境だと感じます。
■ まとめ
令和8年度からの制度変更によって、国立大学法人職員試験はより多様な層が受験しやすくなる一方、知能分野が重視される試験になります。
公務員試験の勉強を進めている方にとっては、大きなチャンスです。
この記事の動画はこちら↓